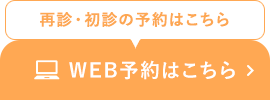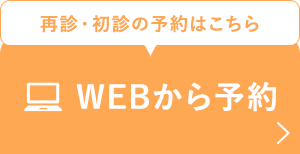起立性調節障害とは
 自律神経の異常によって、立ち上がる時に身体や脳への血流が悪くなる疾患です。思春期に起こりやすく、中学生の約10人に1人が当てはまると言われています。特に中学生に多い傾向にありますが、小学校低学年でも、けっして珍しくはありません。
自律神経の異常によって、立ち上がる時に身体や脳への血流が悪くなる疾患です。思春期に起こりやすく、中学生の約10人に1人が当てはまると言われています。特に中学生に多い傾向にありますが、小学校低学年でも、けっして珍しくはありません。
また不登校のお子さんの3〜4割が起立性調節障害を抱えているというデータもあるようです。 症状は午前中に起こり、午後からは元気になるケースが多い傾向です。夜になるとさらに気分が良くなり、「目がさえて眠れない」と悩む方もいます。
自律神経は2種類あり、交感神経と副交感神経に分かれます。活動している時には交感神経が、身体を休める時には副交感神経が活発化します。
交感神経はストレスに左右されやすく、ストレスを受けると交感神経が優位になります。交感神経ばかり働くと心身に不調が生じやすくなります。
症状
- 何度も立ちくらみやめまいを起こす
- 朝なかなか起きられない、午前中は元気が出ない
- 立ち続けると気分が悪くなる
- 少し動いただけで動悸や息切れがする
- 嫌なことを見たり聞いたりすると気分が悪くなる
- お風呂に入ると気分が悪くなる
- 顔色が青白い
- 朝は食欲がない
- 時々お腹が痛くなる
- だるい、疲れやすい
- 頭が痛くなる
- 乗り物酔いをしやすい
- ※上記の3つ以上を満たす場合、もしくは2つでも症状が強いとき
日常生活での注意点
起床時
 寝ている状態、または座っている状態から、すぐに立ち上がらないようにしましょう。寝た状態からまずは座って30秒以上かけ、中腰となり少しずつ立ち上がりましょう。また、朝礼などで長時間静止して立つことは避け、足を交差させたり、足踏みをしたりすることで、下肢に血液が滞留するのを防ぐことができると言われています。
寝ている状態、または座っている状態から、すぐに立ち上がらないようにしましょう。寝た状態からまずは座って30秒以上かけ、中腰となり少しずつ立ち上がりましょう。また、朝礼などで長時間静止して立つことは避け、足を交差させたり、足踏みをしたりすることで、下肢に血液が滞留するのを防ぐことができると言われています。
暑い日
 暑い日は血圧が下がりやすいです。体育の授業で見学する際は、日陰か室内にいましょう。
暑い日は血圧が下がりやすいです。体育の授業で見学する際は、日陰か室内にいましょう。
規則正しい生活
 早寝早起きを守って、朝に太陽の光を浴びましょう。
早寝早起きを守って、朝に太陽の光を浴びましょう。
日中はできる限り、横にならずに過ごしましょう。
朝起きるのが難しい場合は、無理のない範囲で起きる時間帯を一定にし、必ず決めた時間に起きるように習慣付けましょう。
食事の工夫
 治療の基本は、循環血液量を増やすことにあります。そのための最も簡単で効果的な方法が、十分な水分と塩分の摂取です。ガイドラインでも、1日に1.5〜2リットルの水分と、通常の食事に加えて3g程度の塩分を摂取することが具体的に推奨されてます。薬物療法の効果も、この基本的な水分・塩分摂取が前提となります。
治療の基本は、循環血液量を増やすことにあります。そのための最も簡単で効果的な方法が、十分な水分と塩分の摂取です。ガイドラインでも、1日に1.5〜2リットルの水分と、通常の食事に加えて3g程度の塩分を摂取することが具体的に推奨されてます。薬物療法の効果も、この基本的な水分・塩分摂取が前提となります。
適度な運動
 長期の不活動は、単に体力を低下させるだけでなく、「デコンディショニング」と呼ばれる状態を引き起こし、病状を悪化させる二次的な要因となります。デコンディショニングとは、不活動によって筋力のみならず、心臓や血管を調節する自律神経そのものの機能が低下してしまう現象です。自律神経が「なまる」ことで、わずかな起立負荷にも耐えられなくなり、症状が悪化するという悪循環が生じます。元気になりやすい夕方に、15~30分ほどウォーキングしましょう。重力に影響されない水泳もお勧めします。
長期の不活動は、単に体力を低下させるだけでなく、「デコンディショニング」と呼ばれる状態を引き起こし、病状を悪化させる二次的な要因となります。デコンディショニングとは、不活動によって筋力のみならず、心臓や血管を調節する自律神経そのものの機能が低下してしまう現象です。自律神経が「なまる」ことで、わずかな起立負荷にも耐えられなくなり、症状が悪化するという悪循環が生じます。元気になりやすい夕方に、15~30分ほどウォーキングしましょう。重力に影響されない水泳もお勧めします。
薬物治療
 ミドドリン塩酸塩(商品名:メトリジン®):本剤は血管を直接収縮させ、血圧を上昇させる作用を持つ 。これにより、起立時の血圧低下を防ぎ、立ちくらみなどの症状を緩和します。
ミドドリン塩酸塩(商品名:メトリジン®):本剤は血管を直接収縮させ、血圧を上昇させる作用を持つ 。これにより、起立時の血圧低下を防ぎ、立ちくらみなどの症状を緩和します。
アメジニウムメチル硫酸塩(商品名:リズミック®):ミドドリン塩酸塩で効果が不十分な場合、交感神経の機能を促進して血圧を上げる効果を期待して使用されます。
ピリドスチグミン臭化物(商品名:メスチノン®): 本剤はアセチルコリンエステラーゼ阻害薬であり、自律神経節における神経伝達を増強することで、血管の緊張を高め、起立時の過度な心拍数上昇を抑制する効果が期待されます。海外の複数の研究で起立不耐性に対する有効性が示唆されていますが、日本ではODに対する保険適用はありません。現時点での日本の標準治療ではないため自費診療にて、ご相談に乗らせていただきます。
※起立性調節障害は、治るまである程度の時間を要します。焦ってしまうかもしれませんが、ゆっくり治療を受け続けましょう。
※当院では、患者様とゆっくりお話しできるよう、診察時間を長めに取っています。OD検査や血液検査を行ってから診断し、治療を始めます。
※当院では、心理カウンセラーや児童精神をエキスパートとする医師は在籍していません。患者様の容態によっては当院での治療が難しい場合もあり、その場合は他院へご紹介します。予めご了承ください。
※受診を希望される際は、お電話からご予約ください。