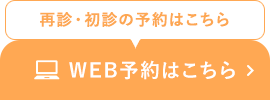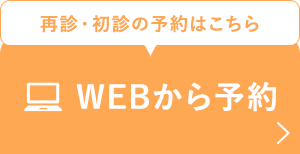【小児科医が徹底解説】小児科は何歳まで?中学生・高校生の受診、移行期の不安に答えます|杉並区・荻窪 長田こどもクリニック
インターネットで医療情報を検索する中で、各施設の先生方の個人的な意見も多く、どこまでが客観的な事実なのか分かりにくい、と感じたことはありませんか?私たち杉並区荻窪の長田こどもクリニックは、そうした保護者の皆さまの不安に応えるため、明確なエビデンス(科学的根拠)に基づいたブログ作成を心がけています。この記事も、世界中の医師が信頼を寄せる最新の医学論文レビューや、日本の公的機関の推奨を基に、他の医療者から見ても妥当だと思っていただけるレベルで、「小児科は何歳まで?」という疑問に徹底的にお答えします。
目次
はじめに:「小児科は何歳まで?」答えが一つではない理由
「小児科って、いったい何歳までかかっていいの?」— お子さまが成長し、中学生、高校生になるにつれて、多くの保護者の皆さまがこの疑問に直面します。風邪をひいた時、昔からのかかりつけの小児科に行くべきか、それとも大人のように内科を受診すべきか。答えが一つではないため、迷われるのも当然です。
この問題が複雑なのは、「小児」を定義する基準が、法律や医療制度、そして各医療機関の方針によって少しずつ異なるからです。しかし、最も大切なのは、お子さまがその年齢や発達段階において、最も適切で質の高い医療を受けられるのはどこか、という視点です。この記事では、様々な角度からこの問題を解き明かし、保護者の皆さまが自信を持って選択できるよう、道筋を示します。
「小児」の定義:法律、制度、学会で異なる年齢
「小児科は何歳まで」という問いに答えるために、まず、様々な場面で使われる「小児」の定義を見てみましょう。
- 法律上の定義:日本の「児童福祉法」では「18歳に満たない者」を児童と定義しています。これが一つの大きな区切りとなります。
- 医療制度上の区切り:自治体が発行する子どもの医療費助成受給券(いわゆる「マル乳」「マル子」などの医療証)の対象年齢も、判断基準の一つになります。多くの自治体では、15歳年度末(中学校卒業まで)や18歳年度末までとなっています。
- 日本小児科学会の考え方:日本小児科学会は、小児科医が対象とする範囲を「子どもが自立した成人になるまで」とし、具体的には「思春期を越え、若年成人に達するまで」としています。これは、年齢で一律に区切るのではなく、身体的・精神的な発達を継続的に見ていく「成育医療」という考え方に基づいています。
このように、基準によって「15歳」「18歳」「20歳頃」と、幅があることが分かります。つまり、「何歳になったら絶対ダメ」という厳密なルールはないのです。
なぜ小児科医が思春期も診るべきなのか?
「中学生にもなれば、もう大人と同じでしょう?」と思われるかもしれません。しかし、思春期は子どもから大人へと移行する、非常に特殊でデリケートな時期です。この時期のお子さまを小児科医が診察することには、大きなメリットがあります。
1. 成長と発達の専門家であること
小児科医は、単に病気を治すだけでなく、生まれた瞬間から思春期に至るまでの、正常な成長・発達の過程を熟知しています。例えば、同じ「腹痛」という症状でも、その背景に成長期特有の問題が隠れていないか、心理的なストレスが関与していないか、といった多角的な視点で診察することができます。
2. これまでの成長記録を知っている「かかりつけ医」であること
乳幼児期からの予防接種や、過去のアレルギー、繰り返した感染症など、お子さまの健康に関する全ての記録を把握しているのが、かかりつけの小児科医です。この「縦のつながり」は、現在の症状を診断する上で、非常に貴重な情報となります。いきなり内科を受診して、これまでの経緯を一から説明するのとは、得られる情報の質が全く異なります。
3. 思春期特有の心の問題にも配慮できること
思春期は、身体だけでなく心も大きく揺れ動く時期です。起立性調節障害や心因性の腹痛、頭痛など、心理的な要因が体の症状として現れることも少なくありません。小児科医は、こうした心身両面の問題に対応するためのトレーニングを受けており、必要に応じて適切な専門家へ繋ぐ役割も担っています。
小児科から内科へ:上手な「移行」の考え方
とはいえ、いつまでも小児科に通い続けるわけにはいきません。いずれは、成人医療の中心である内科などへスムーズにバトンタッチする必要があります。この小児医療から成人医療への移行プロセスを**「トランジション(移行期医療)」**と呼び、近年非常に重要視されています。
移行のタイミング
明確な年齢はありませんが、一般的には**高校卒業や、20歳を迎えるタイミング**が、移行を考える一つの目安となります。特に、喘息やアレルギー、心臓病などの慢性疾患で定期的に通院しているお子さまの場合は、かかりつけの小児科医と相談しながら、計画的に移行を進めることが大切です。
上手な移行のポイント
- お子さま自身が自分の病気を理解する:中学生くらいになったら、自分の病名や飲んでいる薬の名前、アレルギーの有無などを、お子さま自身が言えるように、少しずつ促していきましょう。
- 自分で症状を説明する練習:診察室で、保護者の方が全て代弁するのではなく、まずはお子さま本人に「今日はどうしたの?」と話す機会を作ってあげてください。
- 紹介状を書いてもらう:小児科から内科へ移行する際には、これまでの治療経過や検査結果をまとめた「紹介状(診療情報提供書)」を書いてもらいましょう。これにより、次の医師への情報伝達がスムーズになります。
「小児科?内科?」迷った時のQ&Aコーナー
A1. はい、**全く問題ありません。むしろ、積極的にかかりつけの小児科を受診してください。** これまでの体質(例えば、風邪をひくと咳が長引きやすい、など)をよく知っている医師が診る方が、的確な診断と治療につながります。
A2. はい、大丈夫です。喘息のような慢性疾患は、長期的な管理が非常に重要です。乳幼児期からあなたの成長と症状の変化を見守ってきたかかりつけの小児科医は、あなたの喘息の「専門家」です。高校卒業までは、安心して小児科でのフォローアップを続けましょう。
A3. 小児科は、お子さまの総合的な健康問題を扱う「プライマリ・ケア」の専門家であると同時に、より専門的な医療への「ゲートウェイ(入り口)」でもあります。もし、診察の結果、消化器内科や循環器内科といった、より専門的な診療が必要だと判断した場合は、私たちが責任をもって、お子さまの年齢や状態に最も適した専門医をご紹介しますので、ご安心ください。
長田こどもクリニックの方針:18歳まで、成長を見守るパートナーとして
ここまで様々な情報をお伝えしてきましたが、最後に、私たち長田こどもクリニックの明確な方針をお伝えします。
当院では、原則として、お子さまの医療費助成制度(医療証)が適用される18歳年度末までを、小児科の対象と考えています。
もちろん、これは厳密なルールではありません。18歳を過ぎても、持病のフォローアップや、ご本人が当院での診療を希望される場合は、可能な限り対応いたします。私たちは、お子さまが生まれた瞬間から、悩み多き思春期を乗り越え、一人の自立した若者として社会へ羽ばたいていくまで、その長い道のりに寄り添う「健康のパートナー」でありたいと願っています。
「こんな年齢で小児科にかかっていいのかな?」などと、ためらう必要は全くありません。お子さまの体のことで心配なことがあれば、いつでも、何歳でも、まずは当院にご相談ください。
部活や塾で忙しい中高生の皆さんも、お仕事でお忙しい保護者の方も、安心して受診できるよう、当院は柔軟な診療体制を整えています。
- 平日(月〜金)は、夜20時まで診療
- 土曜日も、13時まで診療
- クリニック前に、無料の専用駐車場を6台完備
杉並区荻窪で、いつでも頼れるかかりつけ医として、皆さまをお待ちしています。
長田こどもクリニック
杉並区荻窪の小児科・アレルギー科