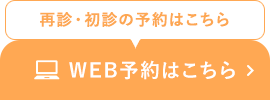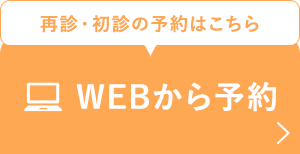【小児科医が徹底解説】溶連菌の症状(のどの痛み・発疹)とは?年齢による違い、正しい診断法まで|杉並区・荻窪 長田こどもクリニック
はじめに:信頼できる医療情報をお探しの保護者の皆さまへ
お子さまが突然の高熱やのどの痛みを訴え、体に発疹が出始めた時、保護者の皆さまはインターネットで様々な情報を検索されることと思います。しかし、多くのウェブサイトでは、医師個人の経験則が強調されていたり、情報の医学的根拠が不明瞭であったりして、「どこまでが真実の情報なのか分かりにくい」と感じられたことはありませんか?
私たち杉並区荻窪の長田こどもクリニックは、そうした保護者の皆さまの不安に応えるため、明確なエビデンス(科学的根拠)に基づいたブログ作成を心がけています。この記事では、お子さまによく見られる「溶連菌感染症」について、世界中の医師が信頼を寄せる最新の医学論文の情報を基に、他の医療者から見ても妥当だと思っていただけるレベルで、徹底解説します。
溶連菌とは?子どもによくある「のどの細菌感染症」
溶連菌(ようれんきん)の正式名称は「A群β溶血性レンサ球菌(Group A Streptococcus、略してGAS)」です。たくさんの種類があるレンサ球菌の一種で、お子さまや若者の細菌性咽頭炎の最も一般的な原因菌です[1]。特に5歳から15歳のお子さまに多く、咽頭炎全体の15〜30%を占めるとされています。
日本では、主に空気が乾燥する冬から春先にかけて流行のピークを迎えますが、年中通して溶連菌感染は消えることはありません。ピーク時期には、お子さまの咽頭炎の35〜40%が溶連菌によるもの、というデータもあります[2]。保育園や学校など、集団生活の場で広がりやすいのが特徴です。
これは溶連菌?年齢で異なる症状の特徴
溶連菌感染症の症状は、お子さまの年齢によって現れ方が少し異なります。特に、3歳を境に、その特徴は大きく変わります。
3歳以上のお子さまの典型的な症状
3歳以上のお子さまでは、症状が比較的はっきりと、かつ突然現れるのが特徴です。
- 突然の高熱とのどの強い痛み:多くは38℃以上の熱が出て、「つばを飲み込むのも痛い」と訴えます。
- 頭痛、腹痛、吐き気:のどの症状だけでなく、全身の症状を伴うことがよくあります[1]。
- のどの所見:診察すると、のどの奥(扁桃腺)が真っ赤に腫れ、白い膿(滲出物)が付いていることがあります。口蓋垂(のどちんこ)が赤く腫れたり、上あごに赤い点々(点状出血)が見られたりするのも特徴的な所見です。
- 首のリンパ節の腫れと痛み:首の前側のリンパ節が腫れて、触ると痛がります。
溶連菌感染症では、一般的な風邪(ウイルス感染症)でよく見られる、鼻水、咳、声がれ、結膜炎、下痢といった症状は、通常あまり見られません。これらの「ウイルスらしい症状」がないのに、突然の高熱とのどの痛みが始まった場合は、溶連菌の可能性を考える重要な手がかりになります。
3歳未満のお子さまの症状:「ストレプトコッコーシス」
3歳未満、特に1歳未満の乳児では、典型的な症状が出にくいことが知られています。「ストレプトコッコーシス」と呼ばれる、少し長引くタイプの症状を呈することがあります。
- 長引く鼻水・鼻づまり
- 38℃以下の微熱が続く
- 機嫌が悪い、食欲がない
- 首のリンパ節の腫れ
「ただの鼻風邪が長引いているな」と思われがちですが、ご兄弟や保育園で溶連菌が流行している場合には、この病態を疑う必要があります[3]。
特徴的な発疹「猩紅熱」— なぜ起こる?特別な治療は必要?
溶連菌感染症の際に見られる特徴的な発疹を「猩紅熱(しょうこうねつ)」と呼びます。これは、溶連菌が作り出す「発赤毒素(ほっせきどくそ)」に対するアレルギー反応(遅延型皮膚反応)によって起こります。そのため、初めて溶連菌に感染した時には出ず、毒素に対する免疫がない場合に現れることがあります。
猩紅熱の発疹の特徴
- 細かい赤い点々:体中に、細かく(1〜2mm)、少しザラザラした感じの赤い発疹が広がります。触ると「サンドペーパー(紙やすり)状」と表現されます。
- 広がり方:最初は脇の下や股のあたりから始まり、そこから体や手足へと広がっていきます。
- イチゴ舌:舌の表面が、ブツブツと赤くなり、まるでイチゴのように見えます。
- 口の周りが白く抜ける:発疹が顔にも広がりますが、鼻や口の周りだけは白く見えるのが特徴的です(口囲蒼白:こういそうはく)。
- 回復期に皮がむける:熱が下がり、発疹が消え始めた頃から、指先などから皮膚が薄くむけてくることがあります(落屑:らくせつ)。
発疹に対する特別な治療は不要です
猩紅熱は見た目が派手なため驚かれるかもしれませんが、発疹そのものに対する特別な塗り薬や飲み薬は必要ありません。 なぜなら、発疹の原因は皮膚の表面にあるのではなく、体内で作られる「毒素」にあるからです。したがって、大元である溶連菌を抗菌薬でしっかりと退治することが、結果的に毒素の産生を止め、発疹を治すための唯一かつ最善の治療となります。通常、抗菌薬を飲み始めると、のどの症状とともに発疹も数日で改善していきます。かゆみが強い場合は、かゆみ止めの飲み薬や塗り薬を対症療法として使うこともあります。
なぜ正確な診断が大切なのか?
「のどが痛いだけなら、風邪と同じでは?」と思われるかもしれません。しかし、溶連菌感染症の診断を正確に行うことには、非常に重要な意味があります。
- 合併症を予防するため:適切な抗菌薬による治療は、後述するリウマチ熱や急性糸球体腎炎といった、まれではあるものの重篤な合併症を防ぐために不可欠です。
- 症状を和らげ、回復を早めるため:抗菌薬は、つらいのどの痛みや熱の期間を短縮する効果があります。
- 他の人への感染を防ぐため:治療を開始して24時間経てば、感染力はほとんどなくなります。集団生活への復帰の目安を明確にするためにも、診断が重要です。
- 不要な抗菌薬の使用を避けるため:逆に、ただの風邪(ウイルス性咽頭炎)に抗菌薬は効きません。正確に診断することで、不必要な抗菌薬の使用を減らし、薬剤耐性菌の増加を防ぐことにも繋がります。
診断方針:症状と検査を組み合わせた、最も確実な方法
溶連菌の診断は、症状だけで判断するのは困難です。研究でも、いくつかの症状を組み合わせたスコアでは、診断の精度が不十分であることが示されています[4]。そのため、当院では症状や周りの流行状況から溶連菌を疑った場合、必ず検査による確認を行います。
迅速抗原検出検査(RADT)
のどを綿棒でこすり、10分程度で結果が分かる迅速検査です。この検査は「特異度」が95%以上と非常に高く、**陽性(+)と出た場合は、ほぼ確実に溶連菌に感染していると診断できます。**
咽頭培養検査
一方で、迅速検査の「感度」は70〜90%と、やや見逃しの可能性があります。つまり、本当は溶連菌がいるのに、迅速検査では陰性(ー)と出てしまうことがあるのです。そのため、アメリカ小児科学会などのガイドラインでは、お子さまにおいて迅速検査が陰性であった場合でも、症状から強く溶連菌が疑われる際には、より精度の高い咽頭培養検査による確認が推奨されています[1]。
当院では、このガイドラインの考え方に則り、症状と迅速検査の結果を総合的に判断し、必要に応じて培養検査を追加することで、見逃しのない、最も確実な診断を追求しています。
お子さまの急な発熱や体調不良は、時間を選びません。当院は、お仕事などで日中の受診が難しい保護者の皆さまにも安心してご利用いただけるよう、以下の診療体制を整えています。
- 平日(月〜金)は、夜20時まで診療
- 土曜日も、13時まで診療
- クリニック前に、無料の専用駐車場を6台完備
杉並区荻窪で、いつでも頼れるかかりつけ医として、お子さまとご家族の健康をサポートします。症状や診断について、少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。