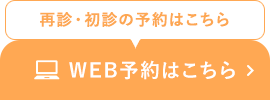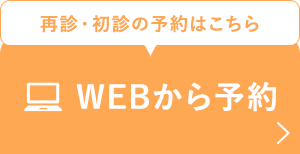【小児科医が徹底解説】溶連菌はいつまでうつる?潜伏期間、登園目安、家族への感染対策まで|杉並区・南荻窪 長田こどもクリニック
はじめに:当院が目指す、エビデンスに基づいた医療情報の発信
お子さまの病気に関する情報を探す中で、多くのウェブサイトが医師個人の経験則に偏っていたり、医学的根拠が不明瞭であったりして、「どこまでが真実の情報なのか分かりにくい」と感じられたことはありませんか?
私たち杉並区南荻窪の長田こどもクリニックは、そうした保護者の皆さまの不安に応えるため、明確なエビデンス(科学的根拠)に基づいたブログ作成を心がけています。この記事では、前回の【症状・診断編】に続き、溶連菌の「感染」にまつわる様々な疑問について、最新の医学論文の情報を基に、他の医療者から見ても妥当だと思っていただけるレベルで、徹底解説します。
溶連菌はどのようにうつる?主な感染経路と潜伏期間
溶連菌は、主に感染している人の咳やくしゃみに含まれる細菌を吸い込むことによる**「飛沫感染」**と、細菌が付着した手でおもちゃやドアノブなどを触り、その手を介して口や鼻に細菌が運ばれる**「接触感染」**によって広がります。ヒトの皮膚や粘膜が唯一の住処(リザーバー)であり、動物からうつることはありません。
潜伏期間:感染してから症状が出るまで
溶連菌に感染してから、のどの痛みや発熱などの症状が出始めるまでの**潜伏期間は、通常2日から5日**です[1]。この期間は、体内で細菌が増殖している段階であり、まだ症状もなければ、他の人にうつす心配もほとんどありません。
最も知りたい「いつまでうつる?」感染力の期間と登園・登校の目安
保護者の皆さまが最も気になるのが、「いつまで他の子にうつしてしまう可能性があるのか」ということでしょう。これには明確な基準があります。
感染力がある期間
溶連菌の感染力が最も強いのは、のどの痛みや発熱などの**症状が活発に出ている急性期**です。治療を受けない場合、症状は2〜5日間続きますが、その間ずっと感染力を持つ可能性があります。
抗菌薬の効果:24時間で感染力はほぼゼロに
溶連菌感染症の治療には、ペニシリン系などの抗菌薬が用いられます。この治療の大きな目的の一つが、感染の拡大を防ぐことです。抗菌薬を飲み始めると、のどにいる溶連菌の数は劇的に減少し、**内服開始から24時間が経過すれば、他の人にうつす力(感染力)は、ほぼなくなることが分かっています[2]。
学校保健安全法では、溶連菌感染症は「条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症」に分類されています。登園・登校を再開するための明確な基準は以下の2点です。
- 適切な抗菌薬による治療を開始してから、24時間以上が経過していること。
- 熱が下がり、全身の状態が良好であること。
この2つの条件を満たしていれば、医師の許可のもと、登園・登校が可能となります。
家族内感染を防ぐために、家庭でできること
学校や保育園と同じくらい、あるいはそれ以上に感染が広がりやすいのが家庭内です。ご兄弟や保護者の方への感染を防ぐために、以下の対策を心がけましょう。
- こまめな手洗い・手指消毒:基本ですが、最も効果的です。特に、感染したお子さまの看病をした後や、食事の前には徹底しましょう。
- 食器やタオルの共用を避ける:感染したお子さまが使ったコップ、お箸、タオルなどは、一時的に分けて使いましょう。
- 咳エチケットの徹底:咳やくしゃみをする際は、マスクやティッシュ、袖で口と鼻を覆うよう、お子さまにも教えてあげてください。
- おもちゃの消毒:小さなお子さまがいるご家庭では、なめたりする可能性のあるおもちゃを、こまめにアルコールなどで消毒するとより安心です。
家族がのどを痛がったら?
もしご家族の中に、のどの痛みや発熱などの症状が出た場合は、早めに医療機関を受診し、溶連菌の検査を受けることをお勧めします。
なぜ抗菌薬を最後まで飲み切るのが重要なのか?合併症のリスクについて
溶連菌感染症では、症状が良くなっても、処方された抗菌薬を途中でやめてはいけない、と指導されます。これは、症状が治まってもまだ体内に生き残っている少数の菌を完全に叩き、**まれではあるものの重篤な合併症を防ぐ**ためです。主な合併症には以下の2つがあります。
① 急性リウマチ熱
溶連菌感染から2〜3週間後に、心臓や関節、神経に炎症が起こる病気です[3]。特に心臓の弁に後遺症を残すことがあるため、予防が非常に重要です。適切な抗菌薬治療を症状が出てから9日以内に開始すれば、リウマチ熱の発症はほぼ完全に防げることが分かっています。
② 急性糸球体腎炎
のどの感染から1〜3週間後に、血尿やむくみ、高血圧といった症状で発症する腎臓の病気です。詳しくは当院の別のブログ記事で解説していますが、こちらも抗菌薬による治療が発症リスクを下げると考えられています。
これらの合併症は、現在では非常にまれになりましたが、ゼロではありません。症状が良くなったからといって自己判断で抗菌薬をやめてしまうと、これらのリスクを高めてしまう可能性があります。処方された抗菌薬は、必ず最後まで飲み切りましょう。
お子さまの急な発熱や体調不良は、時間を選びません。当院は、お仕事などで日中の受診が難しい保護者の皆さまにも安心してご利用いただけるよう、以下の診療体制を整えています。
- 平日(月〜金)は、夜20時まで診療
- 土曜日も、13時まで診療
- クリニック前に、無料の専用駐車場を6台完備
私たちは、単に病気を診断し、薬を処方するだけではありません。なぜこの治療が必要なのか、ご家庭で何に気をつければよいのか、といった情報を、科学的根拠に基づいて丁寧に説明し、保護者の皆さまの不安を解消することも、小児科医の重要な役割だと考えています。杉並区荻窪で、いつでも頼れるかかりつけ医として、お子さまとご家族の健康をトータルでサポートします。