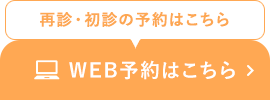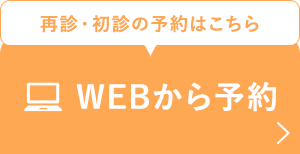もしかして、うちの子の頭の形…?赤ちゃんの「斜頭症」について専門医が解説します
こんにちは、長田こどもクリニックです。
赤ちゃんの頭の形について、多くの情報が溢れてきています。「うちの子の頭、少し歪んでいるかも?」という心配は、現代において珍しいものではありません。特に、片側が平らになっているように見える状態は「斜頭症(しゃとうしょう)」と呼ばれ、近年ご相談が増えている症状の一つです。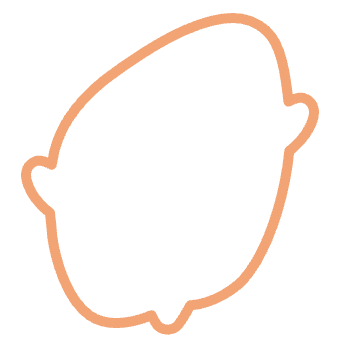
今回の解説では、斜頭症とは何か、その原因、診断方法、そしてどのような対処法があるのかについて、最新の医学的知見に基づき、専門的な観点から詳しくご説明します。
赤ちゃんの頭が歪む「位置的斜頭症」とは?
位置的斜頭症とは、病的な原因がなく、重力による圧迫で赤ちゃんの頭蓋骨が非対称に変形した状態を指します。赤ちゃんの頭蓋骨は、産道を通りやすくするため、また生後の急速な脳の成長に対応するために、とても柔らかく、骨同士がまだ完全にはくっついていません。この柔軟性があるがゆえに、持続的に同じ方向に圧力がかかると、その部分の成長が妨げられ、頭の形がゆがんでしまうのです。
この変形を最も分かりやすく評価するには、赤ちゃんの頭を真上から観察することです。斜頭症の場合、頭の形が平行四辺形のように見えるのが特徴です。これは、圧迫を受けた後頭部が平らになり、その影響で同じ側のおでこが前方に突き出てくるために生じる形状です。
この変形は頭蓋骨自体の問題であり、脳の発達に直接障害を引き起こすものではありません。しかし、その変形の程度により頭全体、さらには顔の歪みにまで発展する可能性があるため、正確な理解と適切な対応が求められます。
お家でできる!赤ちゃんの頭のゆがみチェックリスト【専門医が教える観察ポイント】
保護者の皆様がご自宅で赤ちゃんの頭の形を確認する際、いくつかの重要な観察ポイントがあります。特に、頭を真上から見ることで、非対称性を最も明確に把握できます。当院でも診察する際は真上から、正面、側面から注意深く診察を行っています。
斜頭症の進行度は、いくつかの段階(タイプ)に分けて理解することができます。
- タイプ1:後頭部の平坦化
これが最も初期の兆候です。後頭部の左右どちらか一方が、反対側に比べて平らになっています。 - タイプ2:耳の位置のずれ
変形が進行すると、平坦になった側の耳が、反対側の耳に比べて前方にずれて見えます。これは、頭蓋底の骨を通じて圧力が伝わり、側頭骨が前方に押し出されるために起こります。 - タイプ3:前頭部の突出
さらに変形が進むと、後頭部が平坦になったのと同じ側のおでこが、前へでっぱってきます。これにより、頭の形がより顕著な平行四辺形に見えるようになります。 - タイプ4および5:顔面の非対称性
重度の場合、変形は顔面にまで及びます。平坦になった側の頬が前に突き出し、顔全体が左右非対称に見えることがあります。目の大きさが左右で違って見えたり、鼻がわずかに曲がって見えることも報告されています。
これらの特徴は、単に「後頭部の平らな部分」という問題だけでなく、頭蓋全体に及ぶ三次元的な変形の連鎖として考えることが重要です。重症な場合は後頭部の一点にかかった圧力が、ドミノ倒しのように耳の位置をずらし、前頭部や顔面の骨格にまで影響を及ぼすことがあります。
斜頭症だけじゃない?短頭症・長頭症との見分け方
赤ちゃんの頭の変形には、斜頭症以外にも種類がありますが、斜頭症の頻度が一番高いです。
- 短頭症(たんとうしょう)
「絶壁頭」とも呼ばれ、後頭部全体が左右対称に平らになった状態です。頭の前後が短く、横幅が広く見えるのが特徴で、主に常に真上を向いて寝る赤ちゃんに見られます。 - 長頭症(ちょうとうしょう)
短頭症とは逆に、頭の前後が長く、横幅が狭くなった状態です。未熟児で生まれ、NICU(新生児集中治療室)で横向きに寝る時間が長かった赤ちゃんに見られることがあります。
実際には、これらの変形が単独で生じるだけでなく、「短頭症気味の斜頭症」のように、複数の要素が組み合わさって見られることも少なくありません。いずれも「位置的頭蓋変形症」という大きなカテゴリーに含まれます。ご心配な場合は、我々、専門医にご相談ください。
どうして頭の形が歪むの?斜頭症の2つの主な原因
斜頭症の原因は大きく分けて、赤ちゃんの生活習慣に関連する「位置的要因」と、身体的な特徴に関連する「医学的要因」に分類されます。
原因1:寝かせ方と生活習慣の影響
「Back to Sleep」キャンペーンの影響
以前の”絶壁頭”のブログでも触れましたが、斜頭症の発生率が増加した背景があります。1992年、米国小児科学会は乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクを低減するため、赤ちゃんを仰向けで寝かせることを推奨しました。これによりSIDSの発生率は劇的に減少しましたが、その一方で、赤ちゃんの頭が同じ位置に固定される時間が増え、位置的頭蓋変形の発生率は以前と比べ4倍〜6倍に増加したと報告されています。
一般的なリスク要因
複数の研究により、以下のようなリスク要因が特定されています。
- 向き癖(頭位の好み)
これが最も大きなリスク要因です。赤ちゃんが睡眠中や休息中に、常に頭を同じ方向に向けていると、その側の後頭部に圧力が集中し、平坦化が進行し斜頭症となります。 - タミータイム(腹ばい遊び)の不足
起きている時間に腹ばいになる「タミータイム」は、仰向け寝による後頭部への圧力を分散させる大切な時間です。新生児期から、保護者の監視のもとで短時間から始めることが推奨されています。うつ伏せにしている間は絶対に目を離さず、保護者の方の心に余裕のある時間帯に行いましょう。 - その他の関連因子
研究では、男児であること、第一子であること、吸引分娩などの分娩方法、そして哺乳瓶での授乳(授乳時の体位が一定になりがちなため)なども、斜頭症との関連が指摘されています。
原因2:「筋性斜頸」が隠れているかも?頭のゆがみとの深い関係
位置的要因と並んで重要なのが、医学的要因、特に「先天性筋性斜頸(きんせいしゃけい)」との関連です。
筋性斜頸とは
首にある胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)という筋肉が、生まれつき硬く縮んでいたり、線維化したシコリができる状態です。これは単なる「癖」ではなく、筋肉の物理的な制限によるものです。
筋性斜頸が斜頭症を引き起こすメカニズム
この筋肉の緊張が、斜頭症の直接的な引き金となります。例えば、右側の胸鎖乳突筋が緊張している赤ちゃんは、頭を右に傾け、顔を常に左側に向ける傾向があります。この結果、赤ちゃんは寝ている間も無意識に顔を左に向け続けるため、左後頭部に持続的な圧力がかかり、左側の斜頭症が進行します。
「筋性斜頸 → 向き癖 → 斜頭症」という連鎖は、診断と治療方針を決定する上で非常に重要なポイントです。当院では頭の形だけではなく、背景にあるかもしれない基礎疾患の発見にも力を入れています。
筋性斜頸が向き癖を生み、向き癖は斜頭症を引き起こします。そして、平らになった後頭部は、赤ちゃんにとってより安定して頭を置きやすい「快適な」面となるため、さらにその向きを好み、向き癖が強くなるという悪循環に陥ることがあります。
その他のリスク因子
出生前のリスク因子
- 骨盤位(逆子)あるいは横位などの胎位異常
- 多胎(双子など)
- 子宮の形態異常
出生後のリスク因子
- 早産児
- 脳性麻痺
- 先天性股関節脱臼 ※当院では股関節の診察も行います。
心配な時は専門医へご相談を|正確な診断が大切な理由
赤ちゃんの頭の形に懸念がある場合、自己判断で様子を見るのではなく、ぜひ一度専門医による診察をご検討ください。
専門的な評価は、まず第一に、まれではあるものの治療が必要な病気(頭蓋骨縫合早期癒合症など)を見分けるため、そして第二に、位置的頭蓋変形の重症度を客観的に評価し、ご家庭でのケアや、場合によってはヘルメット治療など、その子にとって最適な治療方針を決定していくために非常に重要です。
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。
当院の「頭のかたち外来」では、お子様の頭のかたち診察し、他の小児科疾患を除外します。また当院では治療を行わないため客観的なデータに基づいてアドバイスを行います。どのヘルメットがお子さんに適切なのかに関してもお子様一人ひとりに最適な治療をアドバイスさせていただきます。
長田こどもクリニックからのお知らせ
【当院の診療について】 お子さんの頭のかたちでお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。
住所: 杉並区南荻窪1-31-14 TEL: 03-3334-2030
杉並区荻窪の小児科 長田こどもクリニック トップページはこちら
ご予約・お問い合わせ
赤ちゃんの頭のかたちに関するお悩み、お気軽にご相談ください。
TEL:03-3334-2030