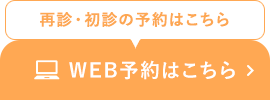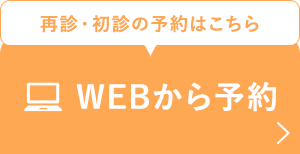【小児科医が徹底解説】水いぼ(伝染性軟属腫)はうつる?プールは?原因から治療法まで|杉並区・荻窪
インターネットで医療情報を検索する中で、多くの情報が個人の経験談であったり、医学的根拠が不明瞭であったりして、「どれが本当に信頼できる情報なのか分かりにくい」と感じたことはありませんか?私たち杉並区荻窪の長田こどもクリニックは、そうした保護者の皆さまの不安に応えるため、明確なエビデンス(科学的根拠)に基づいたブログ作成を心がけています。この記事も、世界中の医師が信頼を寄せる最新の医学論文の情報を基に、他の医療者から見ても妥当だと思っていただけるレベルで、「水いぼ」について徹底解説します。
目次
はじめに:お子さまの水いぼ、どうすればいい?
お子さまの体に、ポツポツとした光沢のあるできものを見つけた時、「これは何だろう?」「痛いのかな?」「他の子にうつる?」と、次から次へと心配事が浮かんでくることでしょう。その正体は、多くの場合**「水いぼ(伝染性軟属腫)」**です。
水いぼは、特にお子さまの間で非常にありふれた皮膚の感染症ですが、その対応については「自然に治るから放っておいて良い」という意見から、「痛くても取るべき」という意見まで、様々な情報が飛び交い、保護者の皆さまを混乱させています。この記事では、そんな水いぼに関するあらゆる疑問に、科学的根拠に基づいて一つひとつ丁寧にお答えしていきます。
水いぼ(伝染性軟属腫)とは?その正体と症状
水いぼの正式名称は「伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ)」です。その名の通り、**伝染性軟属腫ウイルス(MCV)**というポックスウイルスの一種に感染することが原因です[1]。
特徴的な見た目
- 形と色:直径2〜5mm程度の、肌色〜少しピンク色がかった、ドーム状の盛り上がりです。
- 表面:表面はツルツルとして、ろうのような光沢があります。
- 中心のおへそ:よく見ると、中心が少しへこんでいる(中心臍窩:ちゅうしんさいか)のが最大の特徴です。
痛みは通常ありませんが、かゆみを伴うこともあります。体のどこにでもできますが、特に、わきの下、ひじ・ひざの内側、胸、お腹など、皮膚がこすれやすい場所に多く見られます。手のひらや足の裏にできることはありません。
感染経路と潜伏期間:どうやって、いつうつる?
水いぼは、ウイルスが含まれているいぼの内容物や、皮膚の細かなかすに触れることで感染が広がります。
- 直接接触:水いぼがある皮膚と、他の人の皮膚が直接触れ合うことで感染します。
- 間接接触(介達感染):タオルやスポンジなどを共有することで感染します。
- 自家接種:お子さまが水いぼを掻き壊し、その手で体の他の部分を触ることで、自分自身の体で感染を広げてしまうことです。これが、水いぼがどんどん増えていく主な原因です。
「プールでビート板や浮き輪を介してうつる」という話はよく耳にしますが、実はこれを直接証明した質の高い科学的根拠(論文)は、現時点ではありません。米国疾病予防管理センター(CDC)も、「プールでの感染が報告されているが、どのようにして起こるかは証明されていない」としています[2]。多くの専門家は、プールの水そのものではなく、プールサイドでの肌の接触や、タオルの共有といった**「スイミングに関連する活動」**が主な原因だと考えています。ビート板などを介した感染の可能性はゼロではありませんが、過度に恐れる必要はなく、むしろタオルなどを共有しないことの方が重要です。これは一種の**都市伝説**に近いかもしれません。
潜伏期間
ウイルスに感染してから、実際にいぼとして症状が現れるまでの潜伏期間は、**一般的に2〜6週間**ですが、時には1週間から6ヶ月と、非常に幅があります[3]。
自然に治るって本当?水いぼの経過と、赤くなった時のサイン
「水いぼは放っておけば治る」という話は、医学的に正しいです。健康なお子さまであれば、体がウイルスに対する免疫を獲得することで、**多くは6ヶ月から12ヶ月以内に自然に消えていきます。**ただし、個人差が大きく、中には3〜5年かかるお子さまもいます[4]。
赤く腫れてきたら治るサイン?
水いぼの周りの皮膚が赤くなったり、いぼ自体が赤く腫れてきたりすることがあります。これは「Molluscum dermatitis(軟属腫皮膚炎)」や「炎症反応」と呼ばれる状態で、細菌感染(ばい菌が入った状態)と間違われがちです。しかし、多くの場合、これは**体がウイルスを異物として認識し、免疫反応で攻撃を始めたサイン**です。この炎症が起きた後、水いぼが自然に消えていくことが多いため、**治り始めている兆候**と考えることができます[5]。この状態に対して、抗菌薬は必要ありません。
【重要】治療する?しない?小児科医の考え方
「自然に治るなら、何もしなくていいのでは?」と思われるかもしれません。実際、痛みを伴う治療を積極的に行う必要はない、という考え方も、一つの有力な選択肢です。水いぼの治療方針について、世界中で統一された見解はありません。治療を行うかどうかは、以下のメリットとデメリットを天秤にかけて、ご家庭ごとに判断することが大切です。
- 自家接種による拡大や、他の人への感染拡大を防ぐ。
- かゆみを和らげ、掻き壊しによる二次的な細菌感染(とびひ)のリスクを減らす。
- スイミングスクールなど、集団生活での制限を解消する。
- 見た目を気にすることによる、お子さまの心理的なストレスを軽減する。
- 痛みを伴う処置を避けられる。
- 治療による皮膚へのダメージ(色素沈着や傷あと)のリスクがない。
- 通院の負担がない。
当院では、お子さまの性格、水いぼの数や場所、アトピー性皮膚炎の有無など、個々の状況を丁寧にお伺いし、ご家族と一緒に最適な方針を決定します。
これまでの治療法と、これからの新しい選択肢
これまで、水いぼの治療にはいくつかの選択肢がありましたが、それぞれに課題がありました。
痛みを伴う従来法
- ピンセットによる除去(摘除):最も確実で早く治す方法ですが、強い痛みを伴うことが最大の欠点でした。
- 液体窒素による冷凍凝固療法:いぼを凍らせて壊死させる方法です。これも痛みを伴い、色素沈着のリスクがあります。
- 外用薬(カンタリジン):カンタリジンは**意図的に水ぶくれ(ブリスター)を作らせる**ことで、水いぼを脱落させる薬です。そのため、作用機序として**痛みや水ぶくれは必発**です。海外の大規模な臨床試験では、約半数のお子さまで水いぼが完全に消失するという高い効果が示された一方で、痛み、赤み、かゆみといった副反応も多く報告されています[6]がピンセットや液体窒素に比較して処置時の痛みはありません。
治療の選択肢
当院では、お子さまの恐怖心を第一に考え、処置時に痛みを伴わない治療法を積極的に提案しています。
- mBFGクリーム®︎(自費診療):皮膚の再生を促す成長因子を利用したクリームです。痛みがなく、一部のお子さまには有効な場合があります。ただしエビデンスは確立されていません。
- 【新治療】ワイキャンス®︎(保険診療):2024年に承認された、カンタリジンを有効成分とする日本初の水いぼ治療薬です。**当院では、2025年12月より導入予定です。**この薬は医師が塗布するものであり、その作用機序から痛みや水ぶくれを伴いますが、ご家庭での管理のしやすさや、確立されたエビデンスがある点が大きなメリットです。詳しくは、当院の特集記事をご覧ください。
→ 【特集】水いぼの新治療薬ワイキャンス®(カンタリジン)について
水いぼ Q&Aコーナー
A1. はい、**原則として入れます。** 日本臨床皮膚科医会・日本小児皮膚科学会は、プールの水で水いぼがうつることはないため、**「プールの参加を一律に禁止する必要はない」**との統一見解を出しています。ただし、タオルやビート板、浮き輪の共用は避けるべきです。また、掻き壊してじゅくじゅくしている場合は、他の細菌感染のリスクもあるため、治るまで控えた方が良いでしょう。施設によっては独自のルールがある場合もあるため、事前に確認することをお勧めします。
A2. はい、その傾向があります。アトピー性皮膚炎のお子さまは、皮膚のバリア機能が低下しているため、ウイルスが侵入しやすく、また、かゆみで掻き壊してしまうことで、水いぼが広がりやすい(自家接種しやすい)状態にあります。そのため、水いぼの治療と同時に、アトピー性皮膚炎自体のスキンケアと治療をしっかり行い、皮膚の状態を良好に保つことが非常に重要です[7]。
長田こどもクリニックの考え方:親子に寄り添う、新しい選択肢
私たちは、アトピー性皮膚炎をはじめとするお子さまの皮膚疾患に長年向き合う中で、「治療は痛くなく、怖くないものであるべきだ」と常に考えてきました。水いぼ治療における「痛みの問題」は、私たちにとって長年のジレンマでした。
当院では、痛みを伴うピンセットでの除去を第一選択とは考えておりません。お子さまの性格や年齢、水いぼの状態に合わせて、まずは保湿などのスキンケアを徹底し、掻き壊しを防ぐことから始めます。そして、治療を希望される方には、既存の痛くない選択肢に加え、これから標準治療となる「ワイキャンス®︎」についても、最新の正確な情報を提供し、ご家族と一緒に最適な治療法を選択していきます。
お仕事やご兄弟の送迎などで、日中の受診が難しい保護者の皆さまにも安心してご利用いただけるよう、当院は柔軟な診療体制を整えています。
- 平日(月〜金)は、夜20時まで診療
- 土曜日も、13時まで診療
- クリニック前に、無料の専用駐車場を6台完備
杉並区荻窪で、お子さまの皮膚の悩みと、保護者の皆さまの不安に、いつでも寄り添います。