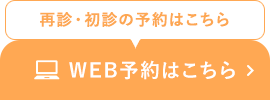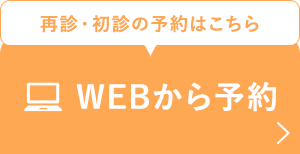【子供が朝起きられない】それ怠けじゃない!起立性調節障害(OD)・自律神経失調症の治し方|親ができること完全ガイド

「毎朝、子どもの部屋のドアを開けるのが憂鬱…」
「また今日も学校に『休みます』の電話をしないといけない…」
そんな日々が続き、つい「なんで起きられないの!」と声を荒らげてしまう、、、しかしお子さんを責める前にまず小児科にご相談ください。
そのつらい症状、もしかしたら単なる怠けや気持ちの問題ではなく、「起立性調節障害(きりつせいちょうせつしょうがい):OD」という、れっきとした身体の病気が原因かもしれません。
ODは決して珍しい病気ではなく、思春期のお子さん、特に中学生の10人に1人が悩んでいると言われています。実際、不登校のお子さんの背景に、この病気が隠れているケースは少なくありません。
この記事は、出口の見えないトンネルの中にいるような不安を抱えるお子さんとご家族のために書きました。ODとは何か、そしてどうすれば改善に向かうのか、クリニックの現場から具体的で実践的な方法を分かりやすくお伝えします。
1.それは怠けじゃない!起立性調節障害(OD)の正体と原因
まず知っていただきたいのは、根性や気合いで治るものではない、ということです。
これは、体の“自動調整機能”である自律神経(じりつしんけい)の不調によって起こります。
私たちの体は、寝ている状態からスッと立ち上がるとき、重力で血液が足元に下がるのを防ぐため、自律神経が瞬時に血管を締めて脳への血流をキープします。
しかし、ODのお子さんはこの自動調整がうまく働きません。
結果として脳の血流が一時的にダウンし、めまいや強いだるさといった、さまざまな不快な症状を引き起こしてしまうのです。
この不調の背景には、急激な身体の成長に自律神経の発達が追いつかないことや、ストレス、遺伝的な体質などが複雑に関係していると考えられています。
2.【症状チェック】うちの子も?当てはまったら要注意のサイン
特徴的な症状として、「午前中に最もつらく、午後になると少しマシになる」というパターンがあります。このせいで、周りから「夜更かししてるだけ」「学校に行きたくないだけ」と誤解され、お子さん自身が深く傷ついていることが本当に多いのです。
以下のサインが見られたら、ODの可能性を考えてみてください。
- □ 立ちくらみ、めまいがひどい
- □ 立っているだけで気分が悪くなる
- □ お風呂で気分が悪くなったり、のぼせやすかったりする
- □ ちょっと動いただけですぐに動悸や息切れがする
- □ 朝、体が鉛のように重くて起き上がれない
- □ 顔色が悪く、青白いとよく言われる
- □ 食欲がなく、特に午前中は何も食べられない
- □ 乗り物酔いがひどい
- □ 原因不明の頭痛や腹痛を繰り返す
これらのうち、3つ以上が当てはまる、あるいは2つでも症状がかなり強い場合は、一度専門家へ相談することをおすすめします。
3.【最重要】OD治療の鉄則|薬の前に“絶対”やるべきこと
「病院に行ったら、すぐ薬をもらえるの?」
そう思われるかもしれませんが、OD治療の主役は薬ではありません。
まずはご自宅で出来ることからしっかり始めることが、改善への一番の近道なのです。
【STEP1:土台】病気の正しい理解と、安心できる環境づくり
【STEP2:中核】生活習慣の見直し(非薬物療法)
【STEP3:仕上げ】薬による治療(薬物療法)
この順番を間違えてしまうと、治療はなかなか前に進みません。
4.今日からできる!OD改善のために家庭でできる2大アプローチ
薬を考える前に、ご家庭でできることが山ほどあります。むしろ、ここを抜きにして回復はありえません。
アプローチ①:叱るのをやめる!安心できる環境こそ最高の治療
ご家族にまずお願いしたい、たった一つのこと。
それは、「ODは体の病気。本人のせいではない」と心から理解し、お子さんに寄り添うことです。
原因不明の体調不良と闘っているお子さん自身が、誰よりも不安で、自分を責めています。
「つらいね」「焦らなくていいよ」
ご家族からのこの一言が、張り詰めた心を溶かし、回復へと向かうエネルギーになります。
- 家庭でできること: 無理やり起こす、叱咤激励する、といった対応は逆効果です。まずはお子さんの「つらい」という気持ちを丸ごと受け止めてあげてください。それが信頼関係の土台になります。
- 学校との連携: クリニックからも説明しますが、ご家族からも担任の先生や養護の先生に病気のことを伝え、協力を仰ぎましょう。「遅刻への配慮」や「保健室登校の許可」など、学校の理解があるだけで、お子さんの心理的プレッシャーは大きく軽減されます。
アプローチ②:生活習慣を“治療”として見直す
これから紹介するのは、単なる健康法ではありません。ODの症状を和らげるための、科学的根拠に基づいた「非薬物療法」という薬物以外の治療です。
- 水分・塩分を意識的に増やす
血液の量を増やして血圧を安定させる、最も簡単で効果的な方法です。スポーツドリンクなどを活用し、1日に水分1.5~2リットル、塩分は普段の食事+3g程度を目安に摂りましょう。 - 「動かなすぎ」を防ぐ
体調が悪いからと寝てばかりいると、筋力だけでなく自律神経の働きそのものが衰える「デコンディショニング」という悪循環に陥ります。調子の良い午後に5分でも10分(可能なら30分)でも散歩するなど、軽い運動を続けることが重要です。 - 起き方・立ち方のコツを掴む
寝た状態から30秒以上かけてゆっくり起き上がる、朝礼などで立つときは足をクロスさせたり、かかとの上げ下ろしをしたりする。こうした小さでも下肢にいく血流を制限して、急な血圧低下を防ぎます。 - 睡眠リズムを整える
夜更かしを助長しないよう、夜のスマホやゲームは時間を決め、なるべく同じ時間にベッドに入る習慣をつけましょう。
5.起立性調節障害の薬物療法|効果と知っておくべきこと
上記の生活改善や環境調整をしっかり行っても、なお週に何度も学校を休むなど、症状が重い場合にはお薬の力を借ります。
- 薬の位置づけ: あくまで治療の補助的な役割です。生活改善という土台があって初めて効果が期待できます。
- 主な薬: 血管を収縮させて血圧を上げる「ミドドリン塩酸塩(メトリジン®)」が主に使われます。症状が最も出やすい午前中に効果を発揮するよう、起床のタイミングで服用することが一般的です。
- 他の薬剤:「アメジニウムメチル硫酸塩(リズミック®)」ミドドリン塩酸塩だけでは効果が不十分な場合に、追加または変更を検討します。頻脈・動悸が主な症状なときは「プロプラノロール塩酸塩(インデラル®)」を使用することもあります。
- 漢方薬:補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)、苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)、小建中湯(しょうけんちゅうとう)などが使用されます。効果が出るまでは1ヶ月以上の内服が必要と思われます。
6.お子さんの未来のために|一人で悩まず、私たちを頼ってください
お子さんがつらい症状と上手に付き合いながら、自信を取り戻し、自分らしい生活や学校生活に復帰できるようにサポートします。
適切な治療と周りの理解があれば、多くのお子さんは光の見える方へ必ず進んでいけます。
「うちの子、もしかして…」
そう思ったら、一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。当院では、お子さんとご家族のお話をじっくりお聞きし、一人ひとりのペースに合わせた治療プランを一緒に考え、伴走していくことをお約束します。
不安な時こそ、すぐ相談!平日夜8時まで、働くパパ・ママをサポートします。
お子さんの体調不良でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。
杉並区荻窪の小児科 長田こどもクリニック トップページはこちら
予約はこちらから
https://c.inet489.jp/osd2030/yoyaku/login.cgi?recno=&birth=
長田こどもクリニック
杉並区南荻窪1-31-14
営業時間:平日毎日よる8時まで、土曜日は13時まで
電話番号:03-3334-2030
https://www.osadaclinic.com/