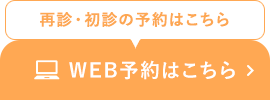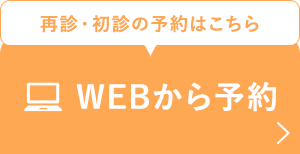【小児科医が徹底解説】鼻から吸うインフルエンザワクチン(フルミスト)は効果ある?注射との違い、副反応を論文で比較|杉並区・荻窪
インフルエンザの季節が近づくと、「注射が痛くてかわいそう…」「鼻から吸うワクチンが日本でもできるようになったと聞いたけど、どうなの?」といったご相談を数多く受けます。特に、注射が苦手なお子さまを持つ保護者の皆さまにとって、「鼻スプレー式」のインフルエンザワクチンは新しい選択肢として注目されています。
私たち杉並区荻窪の長田こどもクリニックは、エビデンス(科学的根拠)に基づいた正確な情報提供を大切にしています。この記事では、国内で承認された鼻スプレー式ワクチン(フルミスト)と従来の注射ワクチンについて、効果や副反応、注意点などを医学論文のデータを基に徹底的に比較し、「結局、どちらがお子さまにとってベストな選択なのか」という問いにお答えします。
目次
鼻スプレー式ワクチン(フルミスト)とは?注射との根本的な違い
まず、2つのワクチンは根本的な種類が異なります。
- 注射ワクチン(不活化ワクチン):ウイルスを処理して感染力を完全になくした(死菌化した)ものの断片を体に入れ、血液中に抗体を作らせるワクチンです。日本で長年、広く使われているのはこのタイプです。
- 鼻スプレー式ワクチン(経鼻弱毒生ワクチン、製品名:フルミスト):病原性を極限まで弱めた生きたウイルスを鼻の粘膜に吹き付けることで、実際の感染に近い形で免疫(血液中の抗体+鼻粘膜の局所免疫)をつけさせるワクチンです。
これまで、フルミストは一部の医療機関が個人輸入して使用する「未承認薬」でしたが、2023年3月に武田薬品工業の「フルミスト点鼻液」が、**2歳以上19歳未満**を対象として日本国内で製造販売承認を取得しました。これにより、国が有効性と安全性を認めた正規のワクチンとして、注射以外の選択肢が正式に加わったことになります。
【効果の比較】感染予防・重症化予防、データで見る実力
「痛くない方がいいけど、効果はどうなの?」というのが一番の関心事でしょう。これについては、数多くの研究が行われています。
感染そのものを防ぐ効果(発症予防効果)
過去には、鼻スプレー式(LAIV)の方が注射(IIV)よりも高い効果を示すという研究結果が多くありました。例えば、複数の研究を統合したメタ解析では、お子さまにおいて、注射(IIV)の有効性が約65%であったのに対し、鼻スプレー式(LAIV)は約80%であったと報告されています[1]。これは、鼻スプレー式がウイルスの侵入口である鼻の粘膜に直接免疫(局所免疫)を作るためだと考えられていました。
しかし、近年の研究では、ワクチンの種類やその年の流行株との相性によって、効果に差が見られないことも多く報告されています。そのため、現在アメリカ疾病予防管理センター(CDC)やアメリカ小児科学会(AAP)は、**「どちらかのワクチンを優先的に推奨する」ということはしていません**[2]。
重症化を防ぐ効果
ワクチンの最大の目的である「重症化予防効果」についてはどうでしょうか。これに関しては、**注射(不活化ワクチン)が重症化や入院、死亡のリスクを大幅に下げるという、非常に強固なエビデンスが蓄積されています**[3][4]。鼻スプレー式にも同様の効果は期待されますが、特にハイリスクのお子さまを守るという観点では、長年の実績がある注射ワクチンへの信頼性は非常に高いと言えます。
効果の持続性
ワクチンの効果は、残念ながら1シーズン限りです。これは、ウイルスの変異と、獲得した免疫が時間と共に弱まるためです。鼻スプレー式の方が持続期間が長いという明確なデータはなく、**どちらのワクチンも、毎年流行シーズン前に接種する必要がある**という点に変わりはありません。
【副反応の比較】注射の痛み vs 鼻の症状
副反応の種類は、ワクチンのタイプによって異なります。
- 注射(不活化ワクチン):最も多いのは、**注射部位の痛み、赤み、腫れ**です。全身性の副反応として、発熱、頭痛、だるさなどが起こることもありますが、通常1〜2日で治まります。
- 鼻スプレー式(生ワクチン):弱毒化したウイルスを鼻に入れるため、風邪の初期症状に似た副反応が出やすいのが特徴です。日本の臨床試験では、59.2%に鼻閉・鼻漏(鼻水・鼻づまり)が見られました。その他、咳やのどの痛み、発熱なども報告されています[5]。これらの症状は、接種後数日をピークに自然に軽快します。
【重要】鼻スプレー式ワクチンが「使えない」ケースと注意点
「痛くない」というメリットがある一方で、鼻スプレー式は生ワクチンのため、接種できない人や、注意すべき点が注射よりも多く存在します。
接種できない、または慎重な判断が必要な人
以下の条件に当てはまるお子さまは、鼻スプレー式ワクチンを接種することができません。これらの場合は、安全性が確立されている注射ワクチンが推奨されます。
- 2歳未満および19歳以上の方(国内での承認対象外のため)
- 喘息の診断を受けている、または過去1年以内に喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)を指摘されたことがある2〜4歳のお子さま
- 心臓病、肺疾患、腎臓病、糖尿病などの慢性疾患をお持ちのお子さま
- 免疫不全の状態(病気や薬によるもの)にあるお子さま
- ご家族など、身近に重度の免疫不全の方がいる場合(ワクチンウイルスが感染するリスクを避けるため、接種後7日間は接触を避けるなどの注意が必要)
【要注意】抗インフルエンザ薬との相互作用
鼻スプレー式ワクチンは生きたウイルスを使うため、**抗インフルエンザ薬(タミフル、リレンザ、イナビル、ゾフルーザなど)と相互作用を起こし、ワクチンの効果が著しく低下する**可能性があります。これは、薬がワクチンウイルスの増殖を抑え込んでしまい、十分な免疫が作られなくなるためです。そのため、接種の前後で一定期間、これらの薬の使用を避ける必要があります。
アメリカCDCの推奨によれば、以下のルールが定められています[6]。
- ワクチン接種前に抗インフルエンザ薬を使用した場合:薬の使用を終えてから、タミフルやリレンザは48時間以上、イナビルは5日以上、ゾフルーザは17日以上あけてから接種する必要があります。
- ワクチン接種後に抗インフルエンザ薬を使用した場合:接種後2週間以内にこれらの薬を使用すると、ワクチンの効果が損なわれる可能性があります。もし、この期間内にインフルエンザに罹患し、治療薬を使用する必要が生じた場合は、ワクチンの効果が不十分であった可能性を考慮し、医師と相談の上、注射の不活化ワクチンによる再接種を検討することがあります。
【接種回数】フルミストは日本では1回接種が基本です
「フルミストは1回で済む」という情報が先行しがちですが、日本の公式なルールは少し複雑です。**日本小児科学会は、2024年9月2日に発表した公式見解の中で、フルミストは接種対象者(2歳以上19歳未満)全員に対して「1シーズン1回接種」としています**[7]。これは、実際の臨床現場における分かりやすさを重視した推奨です。
一方で、フルミストの公式な説明書(添付文書)には、「2歳以上9歳未満で、人生で初めてインフルエンザワクチンを接種するお子さまは2回接種」という記載があります。これは、初めて免疫を獲得する際には2回の刺激でしっかりと免疫を誘導するという考え方(初回免疫)に基づいています。海外ではこの考え方が採用されている国もあります。
しかし、**日本の小児科医が最も重視する日本小児科学会の推奨は「全員1回」**です。これは、過去の接種歴を正確に把握することが困難な場合があることや、接種方法を統一することのメリットなどを考慮した、日本の実情に即した判断と言えます。
これに対し、注射の不活化ワクチンは、日本では従来通り、13歳未満のお子さまは免疫をしっかりつけるために毎年2回接種が基本です。
結論:長田こどもクリニックの考え方
ここまで、注射と鼻スプレー式の違いを詳しく解説してきました。それを踏まえ、当院としてどちらをお勧めするか、結論を述べます。
当院では、アメリカ小児科学会と同様、どちらでも同等の効果が得られると考えています。
フルミストが国内で承認されたことは、選択肢が増えるという点で非常に喜ばしいことです。ただし長期的な安全性に関するデータが注射ワクチンほどには蓄積されていない現状を考慮すると、特に重症化リスクのあるお子さまも含めた全てのお子さまに、最も確実で安心な選択肢は注射ワクチンかもしれません。
注射の痛みを心配されるお気持ちは、私たちもよく分かります。そこで我々は”痛くない注射のワクチン”としてエムラパッチ(局所麻酔薬)の導入をしています。いつでもご相談ください。
お仕事やご兄弟の送迎などで、日中の受診が難しい保護者の皆さまにも安心してご利用いただけるよう、当院は柔軟な診療時間とアクセス環境を整えています。
インフルエンザワクチンは10/1から接種開始!
- 平日(月〜金)は、夜20時まで診療
- 土曜日も、13時まで診療
- クリニック前に、無料の専用駐車場を6台完備
インフルエンザワクチンに関する疑問や不安、接種スケジュールの相談など、どんな些細なことでも構いません。どうぞお気軽にご来院ください。