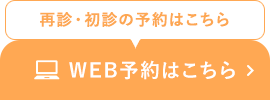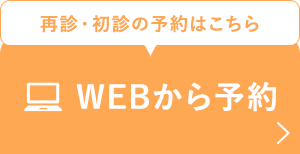「りんご病」名前はかわいいが、意外と深いりんご病。専門医が語る伝染性紅斑の真実
「りんご病」と聞くと、多くの方が子どもの頬が赤くなる、比較的軽症な病気というイメージをお持ちかもしれません。正式名称は「伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)」といい、「りんご病」というかわいい名前とは裏腹に、時には正確な医学的知識と、特別な注意を要する感染症です。
南荻窪にある長田こどもクリニックでは、お子様の健康を守る保護者の皆様に、信頼できる最新の情報を提供することを使命としています。本稿では、小児科専門医の立場から、伝染性紅斑に関する一般的な知識とともに、近年の医学論文で報告されている知見を交え、この感染症について掘り下げて解説します。
特に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを経て、世界的にヒトパルボウイルスB19の活動が活発化しており、2024年から2025年にかけて日本国内でも流行の兆しが見られます。関東地方では既に報告数の増加が報告されており、これは全国的な拡大を示唆するサインだと思われます。2025年7月19日現在、サーベイランスが導入された1999年以降感染者数は最高数を記録しています。
この記事が、りんご病の本当の症状、感染の経路(どううつるか)、紅斑の特徴、そして「病院にいくべきか」を判断する指針となることを願っています。
りんご病(伝染性紅斑)の正体:原因ウイルスと感染の仕組み
病気の犯人:ヒトパルボウイルスB19
伝染性紅斑を引き起こす病原体は、「ヒトパルボウイルスB19」(Human Parvovirus B19、以下B19V)というウイルスです。このウイルスは、非常に小さな単鎖DNAウイルスで、特異的な性質を持っています。
B19Vの最大の特徴は、骨髄にある赤血球の赤ちゃんともいえる赤芽球系前駆細胞に選択的に感染し、増殖する点です。ウイルスは、これらの細胞の表面にある「P抗原」という特定の目印をレセプター(受容体)として結合し、細胞内に侵入します。このメカニズムは、単に皮膚に発疹が出るウイルスというだけでなく、血液を作るシステムに直接悪影響を与えることを意味します。健康な子どもでは、赤血球の寿命が長い(約120日)ため、一時的に赤血球の生産が停止しても大きな問題にはなりにくいのですが、後述する特定の状況下(妊娠中や基礎疾患がある場合)で重篤な合併症を引き起こします。
かかりやすい年齢と感染経路
伝染性紅斑は、主に学童期の子どもたちに流行する病気です。日本の感染症発生動向調査によると、5~9歳での発生が最も多く、次いで0~4歳の幼児にも多く見られます。小児科の定点把握疾患であるため成人の正確な発生数は不明ですが、成人でも感染することは珍しくなく、学生間での集団感染といった事例が報告されています。
主な感染経路は、以下の二つです。
- 飛沫感染:感染者の咳やくしゃみ、会話による飛沫(しぶき)に含まれるウイルスを吸い込むことで感染します。学校や保育園などの集団生活の場で流行やすいのはこのためです。
- 接触感染:ウイルスが付着したおもちゃ、ドアノブ、手すりなどを触った手で、自分の口や鼻、目に触れることで感染します。
また、頻度は低いものの、ウイルスが血液中に存在する「ウイルス血症」の時期にある人から提供された血液製剤を介して感染する可能性も指摘されています。
りんご病の典型的な症状と経過
伝染性紅斑の症状は、特徴的な経過をたどります。感染から発症までの潜伏期間は、通常4日から14日、長い場合は20日ほどです。
第1期:前駆期(発疹前の風邪症状)- 最も感染力が強い時期
特徴的な発疹が現れる約7~10日前に、多くの場合、微熱、頭痛、鼻水、倦怠感といった、ごく軽い風邪のような症状が見られます。この時期は、体内でウイルスが最も活発に増殖し、血液中にウイルスが増えている「ウイルス血症」の状態にあります。そのため、唾液や鼻水にも大量のウイルスが排出され、感染力が最も高くなります。周囲の人は、本人が単なる風邪だと思っている間に感染してしまうのです。この段階でりんご病と診断することは困難です。
第2期:発疹期(特徴的な紅斑の出現)- 診断の手がかり
- 頬の紅斑(平手打ち様紅斑):前駆期の後に現れるのが両頬の紅斑です。境界が鮮明で、まるで平手で叩かれたかのように赤くなるのが特徴で、「slapped-cheek appearance」と表現されます。これが「りんご病」という俗称の由来です。このとき、口の周りだけが蒼白く見える(口囲蒼白)こともあります。
- 体と手足の紅斑(網目状・レース状皮疹):頬の紅斑が出現してから1~数日後、腕や脚(特に伸側)、体幹に網目状あるいはレース状と形容される特徴的な発疹が広がります。この発疹は少し盛り上がることがあり、通常、手のひらや足の裏には現れません。
回復期と発疹の再燃
発疹は通常5~10日ほどで自然に消えていきますが、その後も数週間にわたって、消えたり現れたりを繰り返すことがあります。特に、日光を浴びたり、運動したり、入浴で体が温まったり、精神的なストレスがかかったりすると、一度消えたはずの発疹が再び目立つことがあります。これは病気が悪化したわけではなく、皮膚の血管の反応の名残によるものなので、心配はいりません。
りんご病の経過を正しく理解するために、以下の表に症状と感染力の関係をまとめました。
| 時期 | タイミング | 主な症状 | 感染力 |
|---|---|---|---|
| 潜伏期間 | 感染後4~20日 | 症状なし | なし |
| 前駆期 | 発疹出現の7~10日前 | 微熱、倦怠感、鼻水などの風邪様症状 | 非常に高い |
| 発疹期 | 前駆期の後 | 両頬の紅斑、続いて体や手足に網目状の紅斑 | ほぼ消失 |
| 回復期 | 発疹出現後数週間 | 発疹が消退と再燃を繰り返すことがある | なし |
この表が示す最も重要な点は、見た目に最も派手な紅斑が出現したときには、すでに感染力はほとんどなくなっているという事実です。
「りんご病は、いつ、どのようにうつるか?」
保護者の皆様から最も多く寄せられる質問は、「この病気はうつるか?」そして「いつまでうつるのか?」です。伝染性紅斑の感染力には、他の多くの感染症とは異なる、重要な特徴があります。
感染力と症状の解離
ここまでで説明した通り、伝染性紅斑の感染力がピークに達するのは、特徴的な紅斑が現れる前の、ただの風邪にしか見えない時期です。ウイルスは咳やくしゃみによる飛沫や、ウイルスが付着したものを介して、本人が気づかないうちに周囲へ広がっています。
そして、頬がリンゴのように赤くなり、保護者の方・医療者が「りんご病かもしれない」と気づく頃には、体内の免疫システムがウイルスを抑え込んでいるため、ウイルス血症は終息し、他者への感染力はほぼ消失しています。この「見た目が派手な時期には、もううつらない」という点が、この病気の重要なポイントです。
学校や保育園への登園・登校について
この感染力の特性から、学校保健安全法では、伝染性紅斑は「条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症」の第三種に分類されていますが、通常、発疹期に一律に出席停止とする必要はないとされています。全身の状態が良く、元気に過ごせているのであれば、紅斑が残っていても登園・登校は可能です。
りんご病の流行を防ぐという観点では、発疹が出た子を休ませることには、実はあまり意味がありません。もう皆さんもお分かりの通り、うつるタイミングは発疹が出る前の風邪症状の時期であり、その時点ですでに周囲への伝播は起こってしまっている可能性が高いからです。したがって、流行を完全に食い止めることは極めて困難です。
実践的な予防策
感染力が高い時期には特徴的な症状がないため、りんご病だけを狙った特異的な予防は困難です。したがって、最も効果的な予防策は、日頃からの基本的な感染対策を徹底することです。
- 石鹸と流水による頻繁な手洗い
- 咳やくしゃみをする際に口と鼻を覆う「咳エチケット」の実践
特に、B19Vはノンエンベロープウイルスという種類のウイルスで、アルコール消毒剤が効きにくい可能性があるため、石鹸と手洗いがより重要とされています。
受診のタイミング:「病院にいくべきか?」の専門的判断基準
お子さんの頬が赤くなっているのを見ると、多くの保護者の方は「病院にいくべきか?」と迷われることでしょう。ここでは、専門医の視点から受診を判断するための基準を解説します。
基本的な考え方
健康な子どもが典型的な伝染性紅斑の症状を示し、発疹以外は比較的元気にしている場合、必ずしも急いで医療機関を受診する必要はありません。なぜなら、りんご病には特効薬がなく、治療は症状を和らげる対症療法が中心となり、多くは自然に回復するからです。
しかし、医療機関を受診することには重要な意味があります。我々が診察することで、それが本当に伝染性紅斑なのか、あるいは発疹を伴う他の病気(川崎病、麻疹、風疹など)ではないかを診断できます。第二に、診断が確定することで、家庭内に妊婦さんがいる場合など、適切なアドバイスを受けることができます。
クリニックで何をするのか
小児科では、まず特徴的な発疹の様子や出現の順番などを詳しくお聞きし、視診によって診断します。ほとんどの場合は、この臨床診断で十分です。確定診断が必要な特殊なケース(妊婦への感染が疑われる場合など)では、血液検査でB19Vに対する抗体(IgM抗体)を調べることもあります。
治療については、前述の通りB19Vに直接効く抗ウイルス薬はありません。そのため、発熱や頭痛に対しては解熱鎮痛剤を、かゆみが強い場合には抗ヒスタミン薬を処方するなど、つらい症状を和らげるための対症療法を行います。
【専門医の視点】なぜ今、りんご病が注目されるのか?最新論文から読み解く2024-2025年の世界的流行
パンデミックがもたらした「免疫の空白(Immunity Gap)」
近年、なぜこれほどまでに伝染性紅斑が注目されているのでしょうか。その背景には、COVID-19パンデミックがもたらした、感染症流行の変化があります。2020年から2023年にかけて、マスク着用、手指衛生、ソーシャルディスタンスといった世界規模の公衆衛生対策により、B19Vを含む多くの呼吸器系ウイルスの伝播が劇的に抑制されました。
その結果、この期間中にB19Vに自然に感染して免疫を獲得するはずだった子どもたちの集団が、未感染・免疫獲得しないまま成長しました。これが「免疫の空白(Immunity Gap)」と呼ばれる状態です。社会活動が正常化し、人々の接触が元に戻ると、感受性宿主(ウイルスに感染しやすい人々)が蓄積された集団の中で、ウイルスは再び急速に広がり始めました。これが、現在の世界的な「リバウンド流行」の正体です。
世界的なリバウンド流行の証拠と日本の状況
この現象は、最新の医学論文によって裏付けられています。
- ヨーロッパ:2023年後半からB19Vの感染者数が顕著に増加し、2024年4月にはパンデミック前の平均を33倍も上回るピークを記録したと報告されています。フランスでの研究でも、2023年12月から2024年5月にかけての検査陽性率が、過去5年間と比較して7倍に達したことが示されました。
- アメリカ:同様の傾向が見られ、2024年のB19Vの活動はパンデミック前を上回り、2025年に入ってもその勢いは続いていると米国疾病予防管理センター(CDC)が報告し、医療関係者への注意喚起を行っています。
この世界的な潮流は、日本も例外ではありません。国内の感染症発生動向調査によると、数年間の静穏期を経て、2024年秋頃から報告数が増加に転じました。特に、過去の流行パターンと同様に、まず関東地方で報告数の増加が先行し、その後全国へ拡大する傾向が見られています。荻窪を含む首都圏は、まさにこの流行の最前線にあると言えます。
発疹だけではない:最新研究が示すB19Vの新たな側面
さらに、最先端の研究では、B19V感染が自己免疫疾患の引き金になったり、病状を悪化させたりする可能性が示唆されています。ウイルスの一部が人間の体内の成分と似ているために免疫系が自己を攻撃してしまう「分子擬態」などのメカニズムを介して、関節リウマチや全身性エリテマトーデスといった自己免疫疾患との関連が指摘されています。これはまだ研究段階の知見ですが、B19Vが単なる子どもの発疹症にとどまらない、複雑な側面を持つことを示唆しています。
特別な注意が必要な方へ:妊婦さんと基礎疾患をお持ちの方のリスク
伝染性紅斑は、ほとんどの子どもにとっては軽症で済む病気ですが、特定の条件下では深刻な症状を引き起こす可能性があります。この項では、特に注意が必要な方々について解説します。
妊婦さんとお腹の赤ちゃんへのリスク
免疫のない(過去に感染したことがない)妊婦さんがB19Vに感染した場合、ウイルスが胎盤を通過して胎児に感染することがあります。
- 最も危険な時期:特にリスクが高いのは、胎児の造血機能が活発な妊娠初期から中期(特に妊娠20週未満)です。
- なにが起こるか:胎児に感染すると、B19Vは胎児の赤芽球前駆細胞を破壊し、重度の貧血を引き起こします。この重度の貧血が原因で、胎児の全身がむくんでしまう「胎児水腫(たいじすいしゅ)」という、生命を脅かす状態に陥ることがあります。最悪の場合、流産や死産に至る可能性も報告されています。統計的には、母体が感染した場合の胎児感染率は約20~30%、そのうち約10%が胎児水腫を発症し、胎児死亡率は全体で6%程度とされています。
- 妊婦さんへのアドバイス:
- 流行期には、風邪症状のある人との接触を避け、手洗いや食器の共有をしないなどの基本的な感染対策を徹底してください。マスクの着用も有効な予防策となり得ます。
- 感染が疑われる症状(発熱、発疹、関節痛)が出たり、りんご病の子どもと濃厚接触したりした場合は、かかりつけの産婦人科医に相談してください。
- 産婦人科では、血液検査で抗体の有無(IgG抗体があれば過去に感染済みで免疫あり、IgM抗体があれば最近の感染)を調べ、感染の有無やリスクを評価することがあります。
- 感染が確認された場合やリスクが高い場合は、超音波検査で胎児水腫の兆候がないかなどを慎重に経過観察します。
基礎疾患をお持ちの方のリスク
- 溶血性貧血の方:鎌状赤血球症や遺伝性球状赤血球症など、もともと赤血球が壊れやすい病気(溶血性貧血)をお持ちの方がB19Vに感染すると、「一過性骨髄無形成発作(transient aplastic crisis)」という危険な状態に陥ることがあります。これは、基礎疾患による寿命の短い赤血球が、ウイルスの影響で生産までストップしてしまうために起こる重篤な貧血発作で、緊急の輸血が必要になることがあります。
- 免疫不全の方:免疫機能が低下している方では、ウイルスを体内から排除できずに感染が慢性化し、持続的な貧血を引き起こすことがあります。
大人が感染した場合
大人が伝染性紅斑に感染すると、子どもとは異なる症状が出やすいことが知られています。子どもでは稀な、強い関節痛や関節の腫れ(関節症)が高頻度に見られます。この関節痛は、手首、手指、膝、足首などに起こりやすく、数週間から数ヶ月続くこともあり、時には関節リウマチと見分けがつきにくいほどです。
まとめと長田こどもクリニックからのメッセージ
今回の記事では、伝染性紅斑(りんご病)について、最新の知見を交えて詳しく解説しました。最後に、保護者の皆様に知っておいていただきたい重要なポイントをまとめます。
- りんご病(伝染性紅斑)はヒトパルボウイルスB19が原因で、2024年から2025年にかけて世界的な流行の波が日本にも到達しています。
- 主な症状は、風邪症状の後に出現する「平手打ち」されたような頬の紅斑と、レース状の体幹・四肢の発疹です。
- 「うつるか?」という疑問に対しては、「はい、感染力が最も強いのは発疹が出る前の風邪のような症状の時期」というのが答えです。発疹が出た頃には、感染力はほとんどありません。
- 「病院にいくべきか?」については、診断を確定させるため、また高熱や強い倦怠感などの危険なサインがある場合、そしてご家族に妊婦さんなどのハイリスクな方がいるかも含め評価をするために受診していただくといいと思います。
- 特に妊婦さんは、胎児への影響という重大なリスクがあるため、感染予防を徹底し、感染の可能性があれば産婦人科医に相談することが極めて重要です。
りんご病は、時に深刻な合併症を引き起こす可能性がある一方で、感染したほとんどのお子様は後遺症もなく元気に回復します。本稿で提供した情報が、不安を煽るのではなく、正しい知識をもって冷静に行動するための「お守り」となれば幸いです。
南荻窪の長田こどもクリニックでは、お子様のどんな些細な変化やご不安にも、専門的な知見と温かい心で寄り添います。りんご病に限らず、お子様の健康について気になることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
長田こどもクリニックからのお知らせ
【当院の診療について】 お子さんの予防接種でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。
住所: 杉並区南荻窪1-31-14 TEL: 03-3334-2030
杉並区荻窪の小児科 長田こどもクリニック トップページはこちら
ご予約・お問い合わせ
発熱、気道症状、その他に関するお悩み、お気軽にご相談ください。
TEL:03-3334-2030