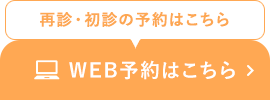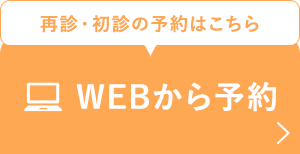作成日:2025年7月14日
更新日:2025年8月7日
多くの親御さんにとって、赤ちゃんの成長は日々の喜びだと思いますが、同時に心配事も尽きないものです。特に、近年赤ちゃんがヘルメットを被っている姿をよく目にすることが増え、自分のこどもも「もしかして絶壁頭?」「左右の形が違う気がする」「頭のかたちが悪いのではないか」といったご心配を抱えていることと思います。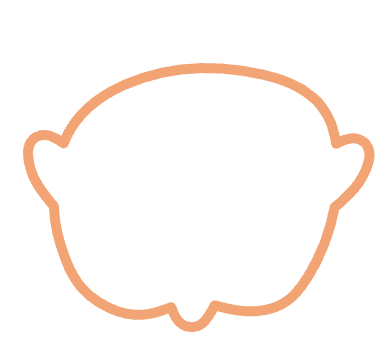
実際、赤ちゃんの頭のかたちに関する相談は、当院でも年々増加しております。このような親御さんの声に応えるため、当院では小児の頭のかたちを専門的に診る「頭のかたち外来」を開設しています。専門的な視点からお子さんの赤ちゃんの頭の形を評価し、親御さんの不安を解消するための適切なアドバイスや治療を提供します。
親御さんが抱える「頭のかたちが悪いかもしれない」という懸念は、見た目の問題だけでなく、大きな心理的負担となっているように感じます。私たちは、そのお悩みに的確にお答えし、どのような選択肢があるのか、出来ることがあるのかなどをアドバイスしています。
赤ちゃんの頭はなぜ変わる?「絶壁頭」の正体とは
赤ちゃんの頭の成長メカニズム
生まれたばかりの赤ちゃんの頭蓋骨は非常に柔らかく、骨と骨の間が完全にくっついていません。これは、脳が急成長するためのスペースを確保するためです。特に生後6ヶ月までは脳が著しく大きくなりますが、この時期の赤ちゃんの頭は持続的な外部からの圧力で形がとても変わりやすい特性を持っています。
位置的頭蓋変形とは?主な3つのタイプ
「位置的頭蓋変形」とは、病気ではなく、外的な圧力によって赤ちゃんの頭の形がゆがんでしまう状態を指します。寝ている時の向き癖などが主な原因です。
これには、主に3つのタイプがあります。
| 種類 | 特徴(見た目の説明) | 主な原因 |
|---|---|---|
| 斜頭症(しゃとうしょう) | 後頭部が斜めにゆがみ、左右非対称に見える。耳の位置がずれることも。 | 向き癖、子宮内での圧迫など |
| 短頭症(たんとうしょう) | 後頭部が平坦に見える、いわゆる「絶壁頭」。頭の幅に対して奥行きが短い。 | 仰向け寝による後頭部への持続的な圧力 |
| 長頭症(ちょうとうしょう) | 頭が前後に長く、後頭部が突き出ている。 | 横向き寝による側頭部への圧力 |
「絶壁頭」(短頭症)が増えた背景
「うちの子、絶壁頭かも…」と心配される方が増えた背景には、医学的な理由があります。1992年、米国小児科学会がSIDS(乳幼児突然死症候群)を防ぐために「仰向け寝」を推奨しました。この推奨が世界に広がることで多くの赤ちゃんの命を救うことに成功しましたが、その一方で、仰向けで寝る時間が増えたことで後頭部に圧力がかかり、絶壁頭を含む位置的頭蓋変形の発生率が大幅に増加したのです。
つまり、「頭のかたちが悪いのは、自分の寝かせ方のせいだ」とご自身を責める必要は全くありません。これは、赤ちゃんの安全を最優先した結果、起こりやすくなった現象なのです。
私は現在40歳で、父(院長)が小児科医でしたが、私はしょっちゅううつぶせ寝で寝ていたそうです。一方で不思議なことに今生きていれば100歳を超える祖父(小児科)は親戚の子どもが生まれると”絶対に赤ちゃんは仰向け寝でなければならない”、と言っていたそうです。米国小児科学会が提唱する40年以上前からそのような考えを持っていたことに驚かされました。
「絶壁頭」は放置して大丈夫?最新研究からわかること
見た目だけじゃない、機能面への影響の可能性
「絶壁頭は見た目の問題」と考えられがちですが、最新の研究では、お子さんの発達や機能面に潜在的な影響を及ぼす可能性が指摘されています。
- 顔の非対称性: 耳の位置、目の大きさ、眉の高さのずれ
- その他: 噛み合わせや聴力への影響を指摘する研究
もちろん、すべてのケースで問題が起きるわけではありませんし、データは未だ少ないため、必発なので治療しようなどと言うつもりはありませんが、「頭のかたちが悪いだけ」と軽視せず、潜在的な影響も考慮して早期に対策を始めることが重要です。
病的な頭蓋変形との見分けと専門医への相談
ごく稀に、「頭蓋骨縫合早期癒合症」という病気が原因で赤ちゃんの頭の形がいびつになることがあります。これは、頭蓋骨が早期にくっついてしまい、脳の成長を妨げる病気で、手術が必要になることもあります。
位置的頭蓋変形との見分けは専門家でなければ困難です。自己判断はせず、赤ちゃんの頭の形で気になることがあれば、必ず専門医に相談しましょう。当院ではヘルメット治療適正使用研修会で研修修了した副院長が診察にあたります。
治療には「タイムリミット」があります。赤ちゃんの頭の成長が活発な生後数ヶ月のうちに発見し、介入することが、改善の大きな鍵を握ります。ご心配があればご相談ください。
ご家庭でできる予防と対策「絶壁頭」にしないために
赤ちゃんの安全のための「仰向け寝」は続けながら、頭のかたちを良くするための工夫を生活に取り入れましょう。
1. 寝かせ方と体位変換
- 向き癖の反対を向かせる: 寝ている時に、いつもと反対側を向くようにそっと顔の向きを変えてあげる。
- ベッドの向きを変える: 赤ちゃんは音や光がする方を向く傾向があります。ベッドの頭と足の向きを日ごとに入れ替えるだけで、自然に向きが変わります。
- バウンサーやカーシートは短時間: 長時間同じ姿勢になる器具の使用は最小限にしましょう。
2. 「タミータイム」(うつぶせ遊び)のすすめ
タミータイムは、起きている時間にうつぶせで遊ばせることで、後頭部への圧力を解放し、首や背中の筋肉を鍛える効果があります。
- 新生児期からスタート: 1日数回、1〜2分から始め、慣れてきたら1回15分程度まで増やしましょう。
- タミータイム中は必ず目をはなすことがないように注意してください。決してうつぶせ寝を推奨するものではありません。
- 必ず固い床の上で: 窒息の危険があるため、柔らかいソファやクッションの上では絶対に行わないでください。
- 親子の遊びの時間に: 「やらなきゃ」と義務にせず、赤ちゃんと遊ぶ時間の一環として楽しく取り入れるのが長続きのコツです。
3. 抱っこや授乳の工夫
無理のない範囲で抱っこや授乳の際も、左右均等になるように意識して向きを変えてあげましょう。
専門的な治療が必要な場合
ご家庭での対策でも改善しない場合や、ゆがみが重度の場合は、専門的な治療が有効です。
ヘルメット治療
ヘルメット治療は、特殊なヘルメットを装着し、赤ちゃんの頭の自然な成長力を利用して頭のかたちを理想的な形に導く治療法です。無理やり締め付けるのではなく、平らな部分が成長するスペースを作ることで、自然に丸い形へ促します。
最新の研究でも、特に重度の絶壁頭(短頭症)や斜頭症に対して、その有効性が報告されています。治療を開始するタイミングは、頭の成長が最も活発な生後早期(3〜6ヶ月頃)が最も効果的です。
筋性斜頸や、股関節脱臼が原因なことも
向き癖の原因が首の筋肉の硬さ(斜頸)や股関節にある場合、適切な診断が必要です。頭の診察とともに一緒に診察します。
まとめ:一人で悩まず、まずは専門家にご相談を
赤ちゃんの頭の形は、生後早期のケアが重要です。「絶壁頭かも」「頭のかたちが悪いのでは?」と感じたら、それは専門家に相談するサインかもしれません。
ご家庭での寝かせ方の工夫やタミータイムは、絶壁頭の予防と改善にとても効果的です。それでも不安が残る場合や、ゆがみが強いと感じる場合は、決して一人で悩まないでください。
当院の「頭のかたち外来」では、お子様の頭のかたち診察し、他の小児科疾患を除外します。また当院では治療を行わないため客観的なデータに基づいてアドバイスを行います。どの多様なヘルメットに関してもお子様一人ひとりに最適な治療をアドバイスさせていただきます。
ご予約・お問い合わせ
赤ちゃんの頭のかたちに関するお悩み、お気軽にご相談ください。
杉並区荻窪の小児科 長田こどもクリニック トップページはこちら
→ ウェブ予約はこちらTEL:03-3334-2030