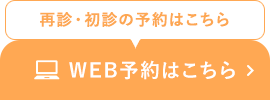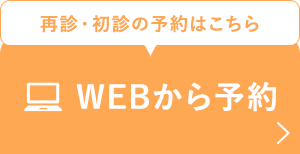杉並区にある長田こどもクリニック副院長の長田洋資です。お子さんの発熱は、親御さんにとって非常に心配なものです。
今回は「解熱剤は飲まない方が早く治るのか?」という疑問に科学的な根拠を元にお話したいと思います。このブログでは、最近の詳しい論文やメタアナリシス(複数の論文結果をまとめたもの)のデータに基づき、発熱のメカニズムから解熱剤の適切な使い方までを、お父さん、お母さんが分かりやすいように解説します。
はじめに:熱はなぜ出るの?〜発熱の「意外な」役割〜
こどもの発熱は、体が病原体と戦うための大切な役割があることをご存知でしょうか。熱が上がると心配になるのは当然ですが、まずは発熱のメカニズムと、その「意外な」メリットについて理解を深めていきましょう。
発熱は体の防御反応である!
発熱は、脳の視床下部という部分が体の「設定温度」を上げることによって起こる、自然な防御メカニズムです。これは、ウイルスや細菌が体に侵入した際に、免疫システムがそれらを異物(本来体の中にいないもの)と感知し、「戦う準備をしろ!」という指令を出すことで引き起こされます。体は自ら熱を上げることで、病原体との戦いに有利な環境を作り出そうとしているのです。
免疫システムと発熱の関係(ウイルスや細菌の増殖抑制、免疫細胞の活性化など)
体温が上がることで、多くのウイルスや細菌は活動が鈍り、増殖が抑えられるとされています。特に38℃を超えると、これらの病原体の活動は著しく低下すると言われています。同時に、白血球やリンパ球といった免疫細胞が活性化し、病原体と戦う力が強まります。また、抗ウイルス物質であるインターフェロンの分泌も促進され、感染症からの回復を早める効果も期待できます。発熱は生物の生存に有利な適応反応として進化してきたと考えられています。
多くの親御さんは高熱をみると、熱の数字そのものを危険視しがちです。また熱が高いこと自体が脳にダメージを与えるのではないか、けいれんを起こすのではないかといった誤解をしていることが多いため、今回のブログでわかりやすく説明したいと思います。
「解熱剤は飲まない方が早く治る」は本当?最新研究の結論
ここまでのお話ですと解熱剤を飲まない方が免疫反応の手助けになり、早く治りそうと思うかもしれません。しかし最新の科学的知見では、一概に「飲まない方が早く治る」とは言えない、複雑な側面があることが分かってきました。研究結果は、病原体の種類や患者の状態によって異なることが示されています。
治癒期間への影響
最近の質の高い研究やメタアナリシスでは、解熱剤を使用しても一般的な急性感染症(特に急性上気道感染症や下気道感染症)の全体的な治癒期間は変わらないと結論付けています。(引用論文: Infect Dis Now. 2023 Aug;53(5):104716. doi: 10.1016/j.idnow.2023.104716.)
ただし、小児を対象としたメタアナリシスでは、解熱剤(アセトアミノフェンやイブプロフェン)の使用が発熱そのものの期間を平均4時間10分短縮する可能性が示されています。これは、あくまで「熱が出ている期間」の短縮であり、病気そのものが治るまでの時間とは異なる点に注意が必要です。
一部の例外として、水痘(水ぼうそう)の場合、アセトアミノフェンを使用した小児において、かさぶたが完全にできるまでの期間がわずかに長くなったという報告があります。これは、解熱剤が皮膚病変の治癒プロセスに影響を与えた可能性を示唆しています。しかしこれは非常に古い論文で対象症例は68名(アセトアミノフェン:37名、プラセボ:31名)と非常に少ないデータしかありません。(引用論文: J Pediatr. 1989 Jun;114(6):1045-8. doi: 10.1016/s0022-3476(89)80461-5. )
また、ある研究では、解熱剤がマラリア原虫の排除期間を延長する可能性が示唆されています。
免疫反応とウイルス排出への影響
古い研究でライノウイルスやインフルエンザウイルス感染症では、解熱剤の使用がウイルス排出期間を延長する傾向があることが示唆されていましたが、最近の成人データではウイルス排泄期間も変わらないというデータとなっています。
また一部の研究では、解熱剤が抗体反応を抑制する可能性も示されており、ワクチン接種後の副反応として解熱剤を使用した場合、ワクチンによる抗体反応を大きく阻害しないという研究結果が出ています。特に接種後に症状が出てから服用する場合には影響が少ないと考えられています。
解熱剤の種類と選び方:アセトアミノフェンとイブプロフェン
お子さんの発熱時に使用される主な解熱剤は、アセトアミノフェンとイブプロフェンです。それぞれ異なる特徴と注意点があるため、適切に使い分けることが大切です。
それぞれの薬剤の作用機序と特徴
アセトアミノフェン(商品名:カロナール、アンヒバ坐剤など)
この薬剤は主に脳の中枢神経系に作用し、発熱や痛みを和らげます。炎症を抑える作用はほとんどありません。胃への負担が少なく、比較的安全性が高いとされていますが、過量投与は肝臓に重篤な負担をかけるリスクがあります。特に小児では体重あたりの用量を厳守することが重要です。
イブプロフェン(商品名:ブルフェンなど)
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の一種で、発熱や痛みを和らげるだけでなく、炎症を抑える作用も持ちます。関節炎や生理痛など、炎症を伴う痛みによく用いられます。胃腸への負担や腎臓への影響がアセトアミノフェンよりも大きい場合があります。そのため、胃腸が弱いお子さんや、脱水気味のお子さんには慎重に使用します。また海外では一般的に生後6ヶ月以上の小児で使用されていますが日本では5歳以上に適応が通っています。
効果と安全性
解熱効果については、2歳未満の乳幼児ではイブプロフェンの方が24時間以内の体温低下効果が高いという研究結果がありますが、全体的にはアセトアミノフェンとイブプロフェンの間に解熱効果の大きな差はないとされています。安全性は、両剤とも適切に使用すれば同等とされていますが、それぞれ異なる副作用のリスクがあります。アセトアミノフェンは肝臓、イブプロフェンは胃腸・腎臓への影響が知られています。日本では慣習的にアセトアミノフェンが主に使用されます。
子どもへの使用における注意点
子どもに安全な解熱剤は限られており、特にインフルエンザ感染時のアスピリン使用は、ライ症候群という重篤な副作用のリスクがあることあります。ですので一般的に小児科ではほぼアセトアミノフェン(カロナール)が使用されます。
お子さんに安全な薬剤選択のため、以下の表を参考にしてください。
表1:お子さんの解熱剤の種類と特徴
| 薬剤名 | 主な作用 | 特徴・注意点 | 代表的な商品名(例) |
|---|---|---|---|
| アセトアミノフェン | 熱を下げる、痛みを和らげる | ・胃への負担が少ない ・肝臓への影響に注意(過量投与) ・効果の持続時間は比較的短い |
カロナール、アンヒバ坐剤、アルピニー坐剤 |
| イブプロフェン | 熱を下げる、痛みを和らげる、炎症を抑える |
・胃腸への負担や腎臓への影響に注意 |
ブルフェン |
| 避けるべき成分 (使用しない) |
・15歳未満、特にインフルエンザ・水痘時はライ症候群のリスクがあるため、絶対に使用しない | アスピリン(バファリン)、ロキソニン、ボルタレン、ポンタール、インテバン、総合感冒薬 | |
親御さんへ:解熱剤を「賢く」使うためのポイント
解熱剤は、お子さんのつらさを和らげるための「道具」です。熱を下げること自体が目的ではなく、お子さんが少しでも楽に過ごせるように、賢く使いましょう。
解熱剤を使う目的:熱を下げること自体ではなく、「つらさを和らげる」こと
お子さんの発熱は、体温の数字そのものよりも、お子さん自身の様子(元気があるか、水分が摂れているか、眠れているか)が重要です。高熱が出ているからといって、必ずしも解熱剤を使用する必要はありません。解熱剤使用の目的は、高熱による不快感(頭痛、体の痛み、だるさなど)を和らげ、水分摂取や睡眠を促し、体力を温存させることです。お子さんが楽になることで、病気と闘うエネルギーを温存し、回復を助けることです。
解熱剤の使用の目安:体温だけでなく、子どもの元気や水分摂取状況を重視する
一般的に38.5℃以上が一つの目安とされますが、たとえ高熱でもお子さんが元気で水分をしっかり摂れているなら、無理に解熱剤を使う必要はありません。逆につらそうでぐったりしている、水分が摂れない、眠れないといった場合は、体温がそれほど高くなくても解熱剤の使用を検討しましょう。お子さんの「つらそう」なサインを見逃さないことが大切です。しかし毎日熱がで続けているようであれば原因検索がやはり重要です。一度受診して風邪と診断されても、再度診察すると中耳炎や喉の所見、皮疹など診断の参考になる所見が変化していることがありますので熱が続けば再度小児科を受診しましょう。
解熱剤の適切な使用法:用法・用量を守ること、自己判断での追加を避けること
医師から処方された解熱剤は、お子さんの体重や年齢に合わせて量が厳密に決められています。必ず指示された用法・用量を守りましょう。市販薬を使用する場合は、必ず薬剤師に相談し、添付文書をよく読んでください。特に、アセトアミノフェンの1回あたりの目安量は体重1kgあたり10~15mg、1日の総量は60mg/kgを超えないように注意が必要です。熱が下がらないからといって、自己判断で服用間隔を短縮したり、追加で服用したりすることは絶対に避けてください。過量投与は重篤な副作用(特に肝臓への負担)につながる可能性があります。坐薬は直腸から吸収されるため、比較的早く効果が現れる傾向があります。
解熱剤以外のケア:水分補給、安静、快適な環境作り
病気の回復には解熱剤だけでなく、水分補給、安静、栄養摂取といった基本的なケアが非常に重要です。発熱時は汗をかきやすく、脱水になりやすいため、こまめな水分補給が最も重要です。経口補水液やお茶、スープなどが良いでしょう。お子さんがぐっすり眠れるよう、静かで快適な環境を整え、無理に食事をさせず、安静に過ごさせましょう。睡眠は免疫力を高め、回復を早めます。厚着をさせすぎず、熱がこもらないように衣類や寝具を調整することも大切です。体が冷えすぎない程度に、心地よい室温を保ちましょう。解熱剤の使用を「病気治療の万能薬」ではなく、「お子さんの快適さを支えるツールの一つ」として位置づけることで、親御さんは体温計の数字に一喜一憂するのではなく、お子さんの全体的な状態を観察し、解熱剤と非薬物療法をバランス良く組み合わせて、より主体的にケアに取り組むことができるようになります。
こんな時はすぐに受診を!〜危険なサインを見逃さないために〜
お子さんの発熱は多くの場合、ウイルス感染ですが、中には専門的な治療が必要なケースがあります。まずは診察を受け、本当にただの風邪なのかしっかり診察をさせてください。また以下のサインが見られた場合は、迷わず医療機関を受診しましょう。早期の受診が、重症化を防ぐために非常に重要です。
親御さんはお子さんの普段の様子を最もよく知っており、その「いつもと違う」という直感は、病気の早期発見において非常に重要です。しかし診察なく問診のみで対応や家での経過観察は重篤なサインを見逃して受診が遅れたりするリスクとなります。特に、熱の数字だけに注目してしまい、お子さんの全体的な状態を見過ごしてしまうことがあります。医療ガイドラインは、具体的な受診基準(月齢、発熱期間、具体的な症状)を提供しており、これらは客観的な判断基準となります。
以下のチェックリストを活用し、「体温の数字よりも、お子さんの様子をよく見てください」というメッセージを強調しつつ、具体的な「危険なサイン」を照らし合わせることで、親御さんの直感を客観的な判断基準と結びつけることができます。これにより、不必要な受診を減らしつつ、本当に必要な医療介入を遅らせないように促すことができます。
表2:こんな時はすぐに受診を!危険なサインチェックリスト
|
項目 |
具体的なサイン |
||
|
月齢・年齢 |
・生後4ヶ月未満の乳児の発熱(38℃以上):すぐに医療機関を受診してください 。免疫機能が未熟なため、重篤な感染症の可能性が高いです。 |
・2歳未満のお子さんで、24時間以上熱が続く場合 。 |
・2歳以上のお子さんで、3日(72時間)以上熱が続く場合 。 |
|
お子さんの様子 |
・活気がない、ぐったりしている、呼びかけへの反応が鈍い、意識が朦朧としている 。 |
・水分が全く摂れない、おしっこが出ない、涙が出ない、口や舌が乾いている、目がくぼんでいるなど、脱水の兆候がある 。 |
・呼吸が苦しそう(ゼーゼーしている、肩で息をしている)、顔色が悪い、唇が紫色。 ・けいれんを起こした(特に初めてのけいれん) 。 |
|
特定の症状 |
・ひどい頭痛、首の硬直(首が曲げにくい) 。 |
・繰り返し吐く、ひどい下痢が続く 。 |
・全身に広がる発疹を伴う発熱。 |
|
その他 |
・基礎疾患(心臓病、腎臓病、免疫不全など)があるお子さんの発熱 。 |
まとめ:親御さんが知っておくべきこと
お子さんの発熱は、親御さんにとって心配の種ですが、正しく理解し、賢く対処することで、不必要な不安を減らし、お子さんの回復をサポートできます。
-
発熱は体の自然な防御反応であり、多くの場合、お子さん自身が病気と戦っている証拠です。熱の数字そのものに過度に心配する必要はありません。
-
解熱剤は「病気を治す薬」ではなく、「つらさを和らげる薬」です。熱の数字にとらわれず、お子さんの元気や快適さを重視し、必要に応じて賢く使いましょう。
-
アセトアミノフェンとイブプロフェンは安全な選択肢ですが、用法・用量を守り、お子さんに使ってはいけない薬(特にアスピリンや総合感冒薬)があることを理解することが非常に重要です。
-
水分補給と安静が、解熱剤と同じくらい大切です。お子さんが快適に過ごせる環境を整え、十分な休息を取らせてあげましょう。
-
お子さんの様子をよく観察し、受診の目安となるサインを見逃さないようにしましょう。迷った時は、遠慮なくかかりつけ医に相談してください。
お子さんの病気は心配なものですが、親御さんの愛情と適切なケアが、お子さんの回復を支える最大の力になります。長田こどもクリニックは、お子さんと親御さんの健康をサポートします。何か不安なことがあれば、いつでもご相談ください。
ご予約・お問い合わせ
発熱、気道症状、その他に関するお悩み、お気軽にご相談ください。
杉並区荻窪の小児科 長田こどもクリニック トップページはこちら
→ ウェブ予約はこちらTEL:03-3334-2030